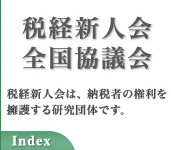|
|
|


特集 第41回大阪全国研究集会・分科会テキスト 第41回大阪全国研究集会・分科会テキスト |
| 滞 納 処 分 |
埼玉税経新人会 |

 |
| 四. 財産の差押と解除 |
 |

| I. 概説 |
| (一)財産の差押 |
 差押の要件(徴47) 差押の要件(徴47)
 督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき 督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき

 超過差押の禁止(徴48 超過差押の禁止(徴48 ) )
 財産の差押は、その強制換価によって国税債権を満足させるために行われるものであるから、国税の徴収に十分な価額の財産を差押えた場合には、それ以外の財産を差押えてはならない。 財産の差押は、その強制換価によって国税債権を満足させるために行われるものであるから、国税の徴収に十分な価額の財産を差押えた場合には、それ以外の財産を差押えてはならない。
 滞納者が、国税債権を超える金額の債権を有する場合 滞納者が、国税債権を超える金額の債権を有する場合
徴63 債権を差押えたときは、差押に係る国税の金額にかかわらず、全額を差押えなければならない。 債権を差押えたときは、差押に係る国税の金額にかかわらず、全額を差押えなければならない。
 滞納金額の5倍に当たる資産譲渡代金未収入金債権の全額差押を適法とした(熊本地裁昭51.9.28)。 滞納金額の5倍に当たる資産譲渡代金未収入金債権の全額差押を適法とした(熊本地裁昭51.9.28)。

 無益な差押の禁止(徴48 無益な差押の禁止(徴48 ) )
 差押えることのできる財産の価額(処分予定価額)が、差押に係る国税の滞納処分費及びその国税に優先する他の債権の合計額を超える見込みがないときは、その財産は差押えることができない。 差押えることのできる財産の価額(処分予定価額)が、差押に係る国税の滞納処分費及びその国税に優先する他の債権の合計額を超える見込みがないときは、その財産は差押えることができない。
 銀行借入の担保に入っている土地・建物を差押えられた場合 銀行借入の担保に入っている土地・建物を差押えられた場合
 土地・建物の見込み時価よりも借入金のほうが多いときは、無益な差押に該当するので、差押の通知を受けた日から2月以内に異議申立を行わなければならない。 土地・建物の見込み時価よりも借入金のほうが多いときは、無益な差押に該当するので、差押の通知を受けた日から2月以内に異議申立を行わなければならない。

 財産の差押 財産の差押
 財産の範囲・差押手続・差押効力発生時期は別表(省略) 財産の範囲・差押手続・差押効力発生時期は別表(省略) |
 |
| (二)差押禁止財産 |
 |
差押禁止財産 |
 |
一般的差押禁止財産(徴75) |
 |
 |
生活上、従事する労働・作業及び社会生活上欠くことのできない財産は、滞納者の承諾があっても、差押できない |
 |
条件付差押禁止財産(徴78) |
 |
国税全額の徴収が可能.換価が容易。第三者の権利の目的となっていない代替財産の提供を条件として差押しないもの |
| 民事執行法131条(差押禁止動産) |
 |
(一)生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品、畳及び建具 |
 |
(二)1月間の生活に必要な食料及び燃料 |
 |
(三)標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭 |
 |
民事執行法施行令第1条 66万円 66万円
 |
 |
給与の差押禁止(徴76) |
 |
源泉税+住民税+社会保険料+生活扶助の金額+体面維持費
生活扶助の金額 100,000円+45,000円×配偶者その他の親族の数(徴令34) 100,000円+45,000円×配偶者その他の親族の数(徴令34)
体面維持費 {給料−(源泉税〜生活扶助費の合計)}× 0.2 {給料−(源泉税〜生活扶助費の合計)}× 0.2
民事執行法152条(差押禁止債権)
給料の3/4に相当する部分(政令で定める額を超えるときは、政令で定める額)は、差押えてはならない。
民事執行法施行令 第2条 第2条 |
 |
 |
一 |
支払期が毎月 |
330,000 |
| 二 |
支払期が毎半月 |
165,000 |
| 三 |
支払期が毎旬 |
110,000 |
| 四 |
支払期が月の整数倍 |
330,000×倍数 |
| 五 |
支払期が毎日 |
11,000 |
| 六 |
支払期が上記以外 |
11,000×日数 |
|
 |
 |
社会保険制度に基づく給付の差押禁止(徴77) |
 |
| (三)差押の解除 |
 |
差押の解除をしなければならない場合(徴79 ) ) |
| i |
納付、充当、更正の取消その他の理由により差押に係る国税の全額が消滅 |
| ii |
差押財産の価額が滞納処分費・差押に係る国税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなったとき(無益な差押) |
| iii |
滞納処分の停止をした場合において、その国税について差押えた財産があるとき (徴153 ) ) |
 |
 |
差押の解除をすることができる場合(徴79 ) ) |
| i |
超過差押になった場合 |
| ii |
代替財産を提供した場合で、その財産を差押えた場合 |
| iii |
納税の猶予を受けた者から解除の申請があった場合(通法48 ) ) |
| iv |
換価の猶予をする場合で必要があると認める場合(徴151 ) ) |
 |
| II. 法律及び運用の実態と問題点 |
 国税徴収法の目的は、「国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保する」ことにある。その特徴は 国税徴収法の目的は、「国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保する」ことにある。その特徴は 自力執行権 自力執行権  国税優先の原則 国税優先の原則  幅広い裁量行政 の三点である。 幅広い裁量行政 の三点である。

 幅広い裁量権を与えられた徴収職員は、 幅広い裁量権を与えられた徴収職員は、

 本当に困っている滞納者には実情を十分聴取・調査・相談し、滞納処分の執行停止を含む緩和措置を最大限適用していく。 本当に困っている滞納者には実情を十分聴取・調査・相談し、滞納処分の執行停止を含む緩和措置を最大限適用していく。

 意図的に納税を回避している滞納者には、徹底した財産調査を行い、差押等の法的措置を講じていく。 意図的に納税を回避している滞納者には、徹底した財産調査を行い、差押等の法的措置を講じていく。
ことを行うことによって、徴収面での公平の確保が図られることになる。
 しかし、滞納税額の増大により、東京、大阪等の大都市の署では1人当たり400〜600件を分担し、手が回らないため、 しかし、滞納税額の増大により、東京、大阪等の大都市の署では1人当たり400〜600件を分担し、手が回らないため、 納税猶予・換価猶予等の納税の緩和措置が形骸化される。 納税猶予・換価猶予等の納税の緩和措置が形骸化される。

 行うべき延滞税の免除も放置される等の問題が発生している。(全国税労働組合「徴収現場からの問題提起」) 行うべき延滞税の免除も放置される等の問題が発生している。(全国税労働組合「徴収現場からの問題提起」)
 「滞納の圧縮は税務行政の当面の最重要課題の一つ」という方針で、徴収職員にハッパをかけるようになり、「売掛金差押」や「捜索」がかなり行われている。 「滞納の圧縮は税務行政の当面の最重要課題の一つ」という方針で、徴収職員にハッパをかけるようになり、「売掛金差押」や「捜索」がかなり行われている。
 消費税等150万円を滞納した業者が2005年1月、熱海税務署に売掛金を差押えられて資金繰りにゆきづまり自殺するという事件が起きた。 消費税等150万円を滞納した業者が2005年1月、熱海税務署に売掛金を差押えられて資金繰りにゆきづまり自殺するという事件が起きた。 |
 |
| III. 問題点解決の方向 |
 消費税の免税点の引下げ、各種所得控除等の縮小により滞納税額は益々増大する方向にある。徴収職員も滞納者の個別事情を考慮する余裕がなく、機械的・一律的に取立が行われることになる。滞納処分により、滞納者の生活が著しく窮迫されないように、滞納者の人権、生存権的財産を守るため、徴収職員と粘り強く交渉しなければならない。強権的な徴収、滞納者を罪人扱いするような取立に対しては、徴税当局と闘っていかなければならない。そのことによって、徴収行政の終局の目的である「納税者の自主納付」がはかられるのではないか。 消費税の免税点の引下げ、各種所得控除等の縮小により滞納税額は益々増大する方向にある。徴収職員も滞納者の個別事情を考慮する余裕がなく、機械的・一律的に取立が行われることになる。滞納処分により、滞納者の生活が著しく窮迫されないように、滞納者の人権、生存権的財産を守るため、徴収職員と粘り強く交渉しなければならない。強権的な徴収、滞納者を罪人扱いするような取立に対しては、徴税当局と闘っていかなければならない。そのことによって、徴収行政の終局の目的である「納税者の自主納付」がはかられるのではないか。 |
| 文責・七海 |
 |
| 五. 納税緩和措置 |
 |

| 【1】納税緩和措置の意義 |
 「申告納税制度の下においては、国税は、その納期限内に自主的に納付すべきものであり、滞納国税を有する納税者に対しては、厳正な態度でその処理に当たることが、徴税の公平な見地からも要請されるところである。 「申告納税制度の下においては、国税は、その納期限内に自主的に納付すべきものであり、滞納国税を有する納税者に対しては、厳正な態度でその処理に当たることが、徴税の公平な見地からも要請されるところである。

 しかしながら、納税者によっては、納期限内における納付又は滞納処分の執行による強制的な徴収手続きを緩和することが納税者の実情に適合し、かつ、徴収上の措置としても妥当とされる場合がある。 しかしながら、納税者によっては、納期限内における納付又は滞納処分の執行による強制的な徴収手続きを緩和することが納税者の実情に適合し、かつ、徴収上の措置としても妥当とされる場合がある。

 納税の猶予等の制度は、このような場合に納税者の実情に即応した措置を講ずることにより、納税者との信頼関係を醸成し、税務行政の適正、かつ、円滑な運営を図ることを目的とするものである」。 納税の猶予等の制度は、このような場合に納税者の実情に即応した措置を講ずることにより、納税者との信頼関係を醸成し、税務行政の適正、かつ、円滑な運営を図ることを目的とするものである」。

 (以上「納税猶予等の取扱要領 昭和51年6月国税庁総則」より)。 (以上「納税猶予等の取扱要領 昭和51年6月国税庁総則」より)。

 これは、「納税者に一定の事実が生じた場合には職権で又は申請や請求によって、納税の緩和措置を認める」という課税権者から納税者に与えられた恩恵的な「裁量権」と読める。 これは、「納税者に一定の事実が生じた場合には職権で又は申請や請求によって、納税の緩和措置を認める」という課税権者から納税者に与えられた恩恵的な「裁量権」と読める。 |
 |
| 【2】納税緩和措置の種類と条文(資料1 「納税緩和措置一覧表」参照) |
 資料1 資料1 |

| (1)納税の猶予 |
 災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予(・・・通46条 災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予(・・・通46条 ) )
 税務署長等は震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合において、その者がその損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税で次に掲げるものがあるときは、政令で定めるところにより、その災害がやんだ日から2月以内にされたその者の申請に基づき、その納期限から1年以内の期間を限り、その国税の全部又は一部の納税の猶予をすることができる。 税務署長等は震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合において、その者がその損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税で次に掲げるものがあるときは、政令で定めるところにより、その災害がやんだ日から2月以内にされたその者の申請に基づき、その納期限から1年以内の期間を限り、その国税の全部又は一部の納税の猶予をすることができる。

 通常の納税の猶予(・・・通46条 通常の納税の猶予(・・・通46条 ) )
 税務署長等は、次の各号の1に該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。 税務署長等は、次の各号の1に該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。

 確定の手続きが遅延した場合の納税の猶予(・・・通46条 確定の手続きが遅延した場合の納税の猶予(・・・通46条 ) )
 税務署長等は、次の各号に掲げる国税の納税者につき、当該各号に掲げる税額に相当する国税を一時に納付することができな い理由があると認められる場合には、その納付することができないと認められる金額を限度として、その国税の納期限内にされたその者の申請に基づき、その納期限から1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。 税務署長等は、次の各号に掲げる国税の納税者につき、当該各号に掲げる税額に相当する国税を一時に納付することができな い理由があると認められる場合には、その納付することができないと認められる金額を限度として、その国税の納期限内にされたその者の申請に基づき、その納期限から1年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。 |
 |
| (2)徴収の猶予 |
 更正の請求があった場合で相当の理由があるとき(・・・通23条 更正の請求があった場合で相当の理由があるとき(・・・通23条 ) )
 税務署長において相当の理由があると認めるときは、その国税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。 税務署長において相当の理由があると認めるときは、その国税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

 異議議審理庁が、必要があると認めるとき(・・・通105条 異議議審理庁が、必要があると認めるとき(・・・通105条 ) )
 意義審理庁は、必要があると認めるときは、異義申立人の申立てにより、又は職権で、異議申立の目的となった処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、またはこれらを命ずることができる。 意義審理庁は、必要があると認めるときは、異義申立人の申立てにより、又は職権で、異議申立の目的となった処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、またはこれらを命ずることができる。

 国税不服審判所長が、必要があると認めるとき(・・・通105条 国税不服審判所長が、必要があると認めるとき(・・・通105条 ) )
 国税不服審判所長は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより、又は職権で、審査請求の目的となった処分に係る国税につき、徴収の権限を有する国税局長・税務署長または税関長の意見をきいたうえ、当該国税の全部又は一部の徴収を猶予し、または滞納処分の続行を停止することを徴収の所轄庁に求めることができる。 国税不服審判所長は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより、又は職権で、審査請求の目的となった処分に係る国税につき、徴収の権限を有する国税局長・税務署長または税関長の意見をきいたうえ、当該国税の全部又は一部の徴収を猶予し、または滞納処分の続行を停止することを徴収の所轄庁に求めることができる。 |
 |
| (3)換価の猶予(・・・徴収法151) |
 税務署長は、滞納者が次の各号の1に該当する場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。 税務署長は、滞納者が次の各号の1に該当する場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。 |
 |
| (4)滞納処分の停止(・・・徴収法153) |
 税務署長は、滞納者につき次の各号の1に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 税務署長は、滞納者につき次の各号の1に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 |
 |
| 【3】問題点 |
 国税庁は平成17年度からはコールセンターでの集中催告や、そこで完結しない事案は専担者が納税者の現預金の把握に努めるなど滞納整理の早期処理を図る方針を打ち出しています。これは、納税者の実情を充分に聞くことなく、「滞納処分・・・売掛金や保険金の差押など」を一網打尽に行う可能性もあるのではないでしょうか。 国税庁は平成17年度からはコールセンターでの集中催告や、そこで完結しない事案は専担者が納税者の現預金の把握に努めるなど滞納整理の早期処理を図る方針を打ち出しています。これは、納税者の実情を充分に聞くことなく、「滞納処分・・・売掛金や保険金の差押など」を一網打尽に行う可能性もあるのではないでしょうか。

 日本大学の北野弘久名誉教授は、「『税務署長等は・・・ できる』とあるのは、するかどうかがいわゆる税務署長の裁量に委ねるという意味ではない。要件を充足する事実があると認められる場合には、・・・しなければならないという意味である」と著書(「税法解釈の個別的研究I」学陽書房)で解説なさっています。 日本大学の北野弘久名誉教授は、「『税務署長等は・・・ できる』とあるのは、するかどうかがいわゆる税務署長の裁量に委ねるという意味ではない。要件を充足する事実があると認められる場合には、・・・しなければならないという意味である」と著書(「税法解釈の個別的研究I」学陽書房)で解説なさっています。

 また民法の権威者である我妻栄氏は国税徴収法の序文で「徴税当局の認定と裁量に委かされている幅が相当に広い。・・・これを承認したのは、納税義務者の態度の如何によってはかような制度を必要とする場合もあると認めたからである」と述べています。 また民法の権威者である我妻栄氏は国税徴収法の序文で「徴税当局の認定と裁量に委かされている幅が相当に広い。・・・これを承認したのは、納税義務者の態度の如何によってはかような制度を必要とする場合もあると認めたからである」と述べています。

 国民主権と人権尊重を基調とする憲法の下では、税法は納税者側の権利立法でなければならず、それゆえに納税緩和措置は納税者の権利として大いに活用し、やむを得ずに滞納してしまっている善良な納税者を「滞納処分」から守っていくことが必要ではないでしょうか。 国民主権と人権尊重を基調とする憲法の下では、税法は納税者側の権利立法でなければならず、それゆえに納税緩和措置は納税者の権利として大いに活用し、やむを得ずに滞納してしまっている善良な納税者を「滞納処分」から守っていくことが必要ではないでしょうか。 |
| 文責・阿部 |
|
|