
| > 社会保障と税の一体改革に関する公述 |
| 「一体改革」と大企業の負担 |
| 埼玉会 菅 隆徳 |
| はじめに |
 |
社会保障も税制改革も、庶民の負担増ではなく、大企業の、能力に応じた公平な負担が求められています。 一方で復興特別法人税は、法人実効税率を5%下げるので、法人税は実質減税。3年経過後は毎年7800億円、20年で15兆6000億円もの減税が続きます。大企業減税、庶民増税、この納得のいかない矛盾を国民はいつまでも許さないでしょう。本稿では、社会保障と大企業負担の関係、大企業減税の歴史的経過について解明します。つづいて庶民増税の一方で累増する大企業の内部留保について、増加要因の歴史的分析と課税のあり方を検討し、大企業内部留保課税の提案を行います。 |
| (1)消費税が社会保障を支えているわけではない なぜなら、現代日本には、社会保障を支えるためであれば消費税増税もやむをえないと思う人たちがかなり多くいるからです。しかし、消費税の社会保障目的税化には、消費税以外の他の所得税等はもはや社会保障には使われなくなると言う、第二の側面があることを忘れてはなりません。社会保障目的税化には、社会保障と消費税とをあたかも二人三脚の関係にするように、固く結びつける役割があります。ここでは、大企業や富裕層から吸い上げた税金が社会保障にまわされる回路が断たれてしまいます。(二宮厚美「社会保障の充実と財源・税制のあり方」『学習の友』2012春闘別冊95頁)財界が「社会保障と税の一体改革」を推進する理由がここにあります。 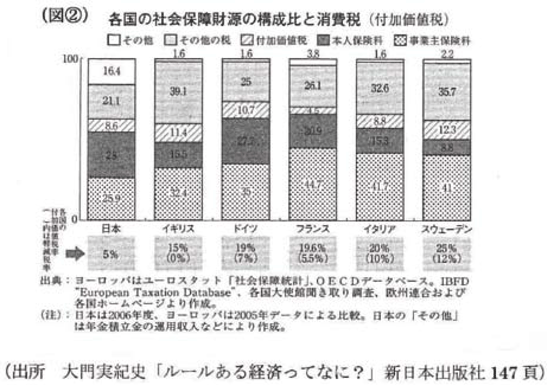 |
(2)大企業の内部留保と大企業減税 |
| (3)内部留保とは何か? |
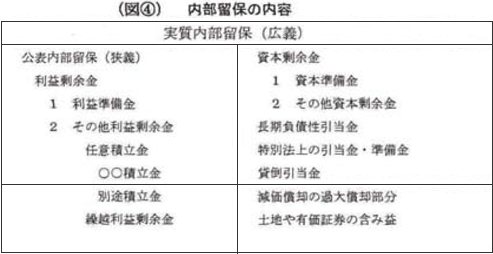 |
|
|
| (4)内部留保はどのようにしてため込まれたのか |
 |
|
|
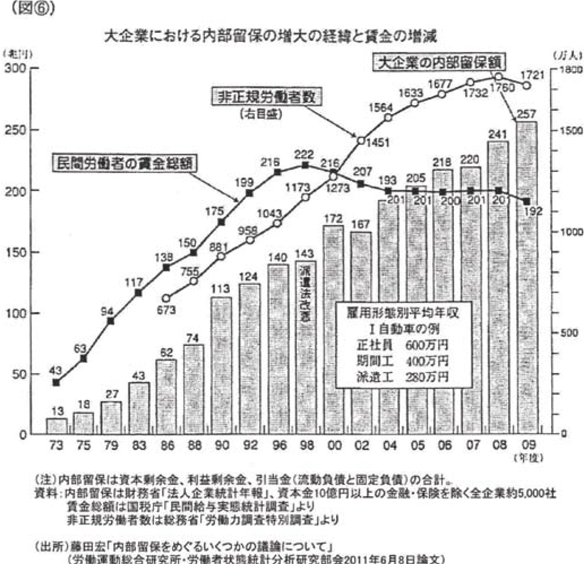 |
|
|
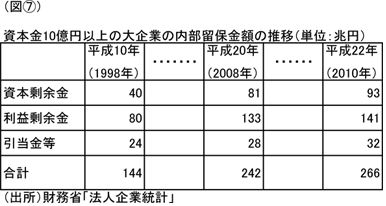 |
|
(図 1)税率引き下げによるもの 31兆円(法人税率42%→ 30%) 2)受取配当益金不算入 12兆円 31兆円(法人税率42‰ → 30‰) 3)研究開発費減税 2兆円 4)連結納税減税 3兆円 5)外国税額控除 2兆円 合計 50兆円 (引当金、準備金の減税額、資本剰余金のプレミアムの非課税は除く) |
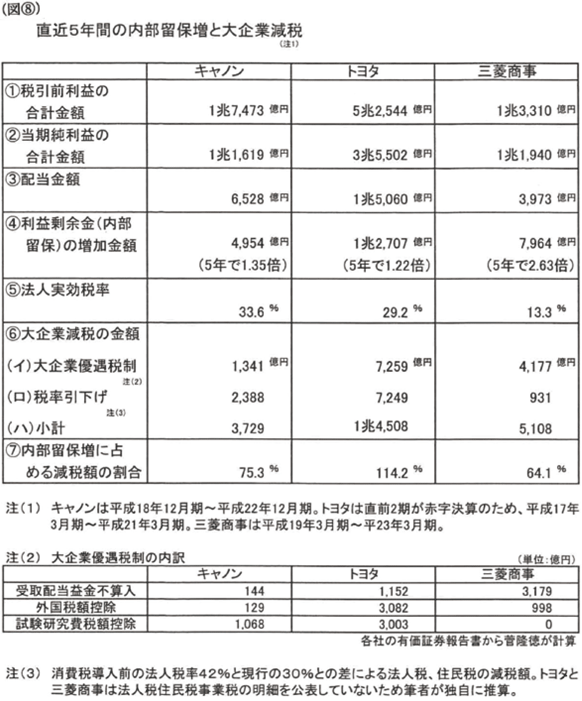 |
| 減税の総額になるのですが、その金額は5年間の利益剰余金(狭義の内部留保)の増額の50%をはるかに超え、3社の単純平均では、91.1%に達しています。内部留保増の大半は、大企業減税によるものといえます。 |
| (5)大企業の財産課税について |
| (6)大企業の内部留保への課税の提案 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
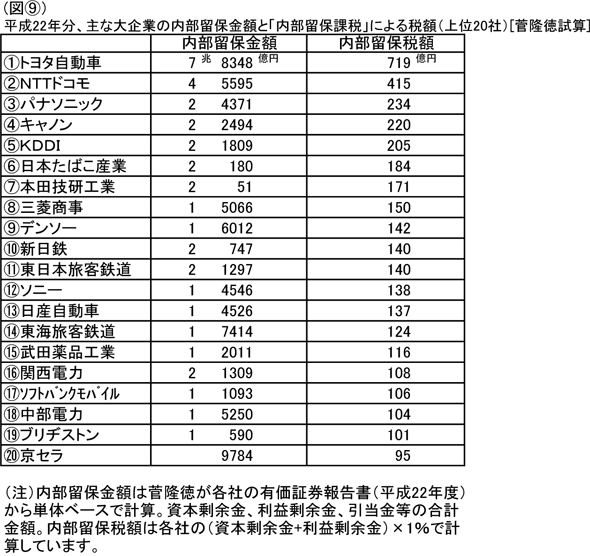 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注 (1)垣内亮「社会保障を口実として庶民大増税」(「前衛」2012年2月号 46頁)。垣内氏は次のように述べています。2007年の1月に経団連が「希望の国、日本」と題した提言を出しました。(「御手洗ビジョン」)この提言には「消費税の増税」と「法人税の減税」が両方とも提案されていました。べつに両者は結び付けて書かれてはいなかったが、御手洗会長(当時)は記者会見で法人税減税の財源を聞かれて、「消費税をあげると明確に書いてある」と答えました。いくら「社会保障のため」とごまかしても、消費税増税の本当の狙いが、大企業減税にあることは明確です。 (2)日本の財界は以前から企業の社会保障負担の軽減を要求しています。「活力と魅力溢れる日本を目指して」(奥田ビジョン2003年)では、「公的年金の基礎年金部分、高齢者医療・介護の財源については、能力に応じて公正・公平な負担を求められる消費税を活用することが望ましい」と述べた上で、「サラリーマンの社会保険料(特に厚生年金、健康保険、介護保険、雇用保険)は、本人と雇用主とのマッチング拠出が前提となっている。これは本来、個人が全額負担するところを事業主が肩代わりするものであり (中略) 企業の従業員についても、自営業者と同様、保険料を全額本人が負担する方法に改めることが考えられる。」としています。経団連は「平成24年度税制改正に関する提言」で、消費税増税を主張する理由として「増え続ける社会保障給付費を企業や現役世代が負担する社会保険料の引き上げで手当てすることには限界がある」として、つまり、自分たちの保険料負担を増やさないために、消費税を増税せよとしています。 (3)山家悠紀夫氏(暮らしと経済研究室)は「大企業では利益剰余金が増え、それは証券投資にまわっている」として、次のように述べています。最近10年余りの大企業の貸借対照表を見ると、著しく増えているのが内部留保(利益剰余金等)です。1997年度末に100兆円そこそこであったものが2009年度末には200兆円超に100兆円以上も増えています。人件費を抑えるなどして利益が膨らんだ上に、減税の恩恵を受けて税負担が軽くなったからです。その増えた内部留保はどこに向かっているのでしょうか。流動資産は変わらず、土地、設備などの固定資産も増えていません。著しく増えているのが「証券等への投資」です。1997年から12年間で140兆円近くも増えています。この12年間、内部留保が著しく増えたけれども、その増えた資金の使い道がなかった。とりあえずは証券運用して、お金でお金を稼がせている・・・ (4)資本準備金について北野弘久教授は次のように述べています。「株式発行差金は、本来、資本市場メカニズムを通じて得られたものであって、資本ではない」(北野弘久『納税者の権利』1981年 岩波新書 132頁)「株式発行差金は、大企業の「現代的利潤」の一つの「投影」であり、一つの「変形」である。税法学的には株式発行差金も大企業の現代的担税力の指標であって、同差金への非課税は租税優遇をもたらす租税特別措置を構成する。」(北野弘久『現代企業税法論』1994年 岩波書店25頁)同じく資本準備金について、駒澤大学の小栗崇資教授は次のように述べています。「資本準備金は企業の財務活動を通じて証券市場から収奪したプレミアム的利益部分が積み立てられる法定準備金です。この資本準備金には株式払い込み剰余金や合併差益、株式交換差益、会社分割差益などがあります。資本準備金の中でももっとも大きな部分を占める株式払い込み剰余金は、株主の払込金額のうち資本金に組み入れられなかった部分です。これは財務活動を通じて実現した利益であり、この利益を資本化したものです。これは株主の払込金額のうち株主が権利行使できない部分であり、利益の内部留保と考えることができます。(小栗崇資、谷江武士編著 『内部留保の経営分析』2010年 学習の友社 101頁) (5)財務省「法人企業統計」による2010年度の内部留保の金額は次の通りです。 (資本金10億円以上の金融・保険業を除く約5000社の場合)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(すが・たかのり) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲上に戻る |