
| > 納税者権利憲章と国税通則法 |
| 2011年度税制改正大綱の検討、その問題点 |
| - 税務行政の強権化・納税者への義務強要、大企業減税、消費税増税地ならし - |
| 東京会 飯島 健夫 |
日本経団連米倉会長は日経新聞の新春インタビューで、今年の最優先すべきは税財政・社会保障の一体改革だとして、「安定的な社会保障の基盤を作るには消費税を早期に10%、ゆくゆくは欧州各国並み(15  20%)に引き上げるべきだ」(日経1/3)と述べ、経済同友会は1月11日「2020年の日本創生」を発表、その中で「消費税率は13年度に10%、15年度に15%、17年度に17%」と3段階の引き上げを提起し、法人実効税率のさらなる引き下げを求めている。日本商工会議所の岡村会頭も「税制の抜本改正、社会保障制度の構築」を求めている。 20%)に引き上げるべきだ」(日経1/3)と述べ、経済同友会は1月11日「2020年の日本創生」を発表、その中で「消費税率は13年度に10%、15年度に15%、17年度に17%」と3段階の引き上げを提起し、法人実効税率のさらなる引き下げを求めている。日本商工会議所の岡村会頭も「税制の抜本改正、社会保障制度の構築」を求めている。 |
|
| [納税環境整備] 1 国税通則法の見直し (1)税務調査における事前通知 (2)税務職員による質問検査権 (3)税務調査終了後における調査内容の説明 (4)修正申告等の勧奨 (5)税務調査における終了通知 (6)納税者から提出された物件の預かり・返還に関する手続 (7)更正の請求期間の延長 (8)更正の請求における「事実を証明する書類」の添付義務化 (9)虚偽の更正請求に対する処罰規定 (10) 処分の理由付記 ※国税通則法一部改正案の題名「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」 |
|
| 2 納税者権利憲章の制定 |
|
| (1) | 納税者の自発的な申告・納税をサポートするため、納税者に提供される各種サービス |
| (2) | 税務手続きの全体像、個々の税務手続きに係る納税者の権利利益や納税者・国税庁に求められる役割・行動 |
| (3) | 国税庁の処分に不服がある場合の救済手続き、税務行政全般に関する苦情等への対応 |
| (4) | 国税庁の使命と税務職員の行動規範 |
東京税財政研究センターの意見書(要約) |
|
< OECDの水準 > |
|
| 3 税務調査手続(平成24年1月1日以後適用) |
|
| (1) | |
|
|
|
|
|
|
|
*<参照>別紙税調資料「税務調査の際の事前通知について」事務運営指針(平13.3.27) |
|
|
|
|
| (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) |
|
|
|
|
|
「確定申告を行った所得300万円超の申告者」 [検討事項](大綱) 1 白色申告者の必要経費の概算控除のあり方 2 正しい記帳をしない者の必要経費のあり方 3 専従者控除のあり方 東京税財政研究センターの意見書(要約) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 更正の請求 |
|
| (1) | |
| (2) | |
| (3) | |
| (4) | |
| (5) | |
| (6) | |
| (7) | |
(1)(2)(5)(6) |
|
(3)(4) |
|
| 東京税財政研究センターの意見書(要約) | |
| [所得税] 1 給与所得控除の見直し(平成24年分以後の所得税から) |
|
| (1) | 給与収入1500万円の245万円を上限とする。 |
| (2) | 役員給与等の収入2000万円超の場合は次のようにする |
245万円ー2000万円を超える部分の金額×12% |
|
185万円 |
|
185万円ー3500万円を超える部分の金額×12% |
|
125万円 |
|
*役員等 法人税法第2条15号規定の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員(特別職、指定職)、地方公務員(国家公務員に準ずる者)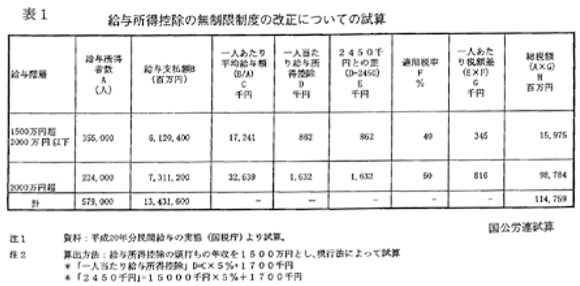 2 特定支出控除の範囲拡大(平成24年分所得税から) 3 退職所得課税の見直し 4 成年扶養控除の見直し(平成24年分所得税から) |
|
| 5 配偶者控除 6 金融証券税制 |
|
| [相続税](平成23年4月1日以後の相続から適用) 1 基礎控除 2 税率 3 死亡保険金 4 未成年者控除 5 障害者控除 |
|
| [贈与税](平成23年1月1日以後の贈与から適用) 1 税率構造を2段階に改正。 (1)20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与税の税率 (2)上記以外の贈与税の税率いずれも最高税率は55%であるが、累進構造が異なる。 2 相続時精算課税制度の見直し (1)受贈者の範囲に20歳以上の孫を追加 (2)贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げる |
|
| [法人税] 1 法人税率 [法人税率×(1+住民税率)+事業税率]÷(1+事業税率) 前提(東京都) 法人住民税20.7% <改正前> [0.3×(1+ 0.207) + 0.0756] ÷(1+0.0756)= 40.69% A <改正後> [0.255×(1+ 0.207)+ 0.0756]÷(1+0.0756)= 35.64% B <引下率> AーB= 5.05%  実効税率5%の法人税率引き下げで、1兆5000億円の減税という試算も示されている。消費税導入以来数次にわたって、法人税率が引き下げられてきたが、「あるところから取る」という税制が貫かれていない。11月4日の税制調査会へ提出された資料でも、「法人税率を引き下げた場合、社員への還元、設備投資の増強、人員の増強といった投資・雇用への充当よりも、内部留保や借入金の返済に充当することを考えている企業が多い」(別紙税調資料)。実効税率を引き下げても、大企業の懐を肥大化させるにすぎない。これらの内部留保は賃金引き上げや税金として社会的に還元されるべきものであろう。 2 減価償却制度 3 欠損金の繰越控除制度(平成23年4月1日以後に開始する事業年度) |
|
|
4 貸倒引当金制度 5 中小企業税制 |
|
| [消費税] 1 事業者免税点制度の見直し(平成24年10月1日以後適用) (1)前年1月1日から6月30日までの課税売上高1000万円超の個人事業者 (2)前事業年度開始の日から6月間の課税売上高1000万円超の法人 (3)以上の適用に当たっては課税売上高の金額に代わって給与等の支払金額を用いることができる。 2 還付申告書 (いいじま・たけお) 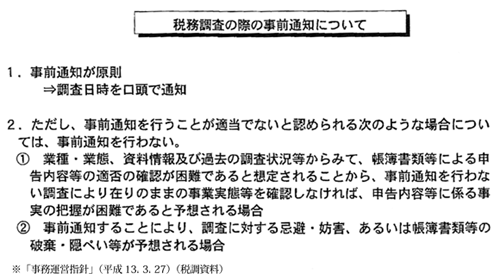 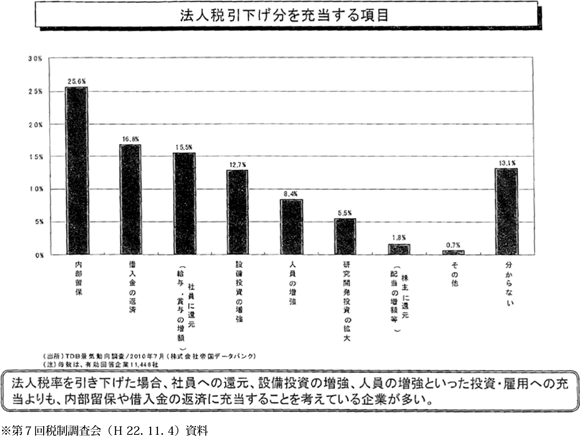 |
|
| ▲上に戻る |