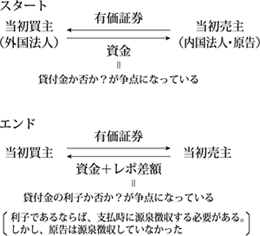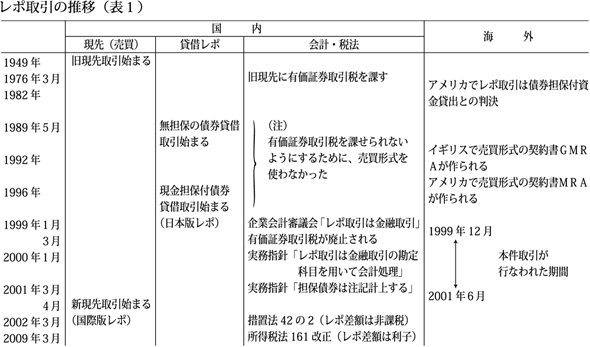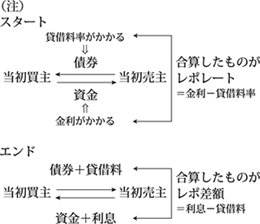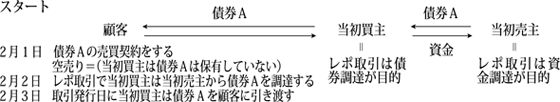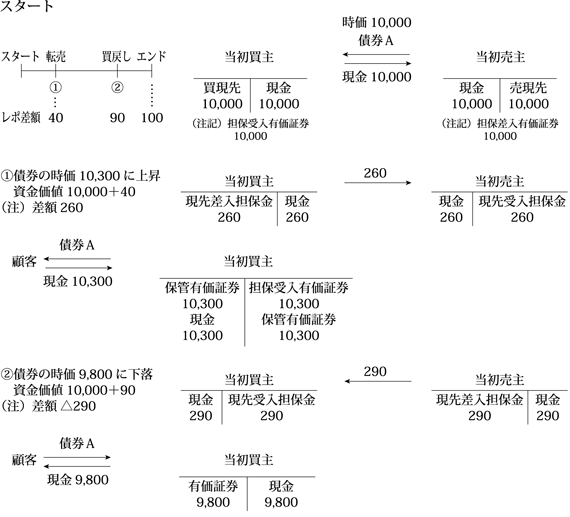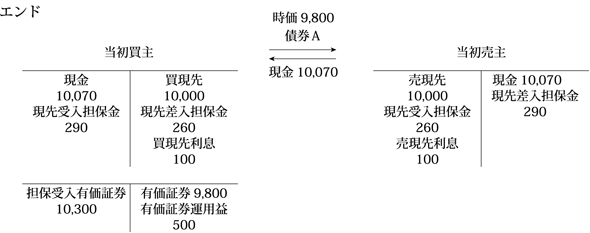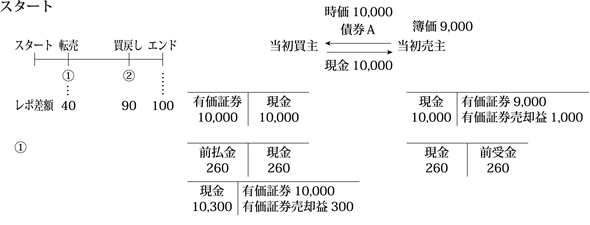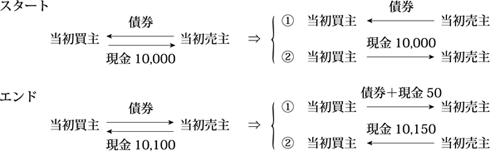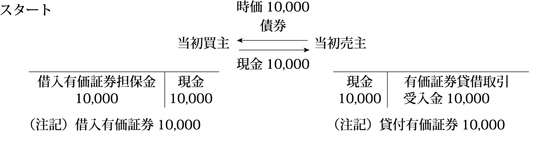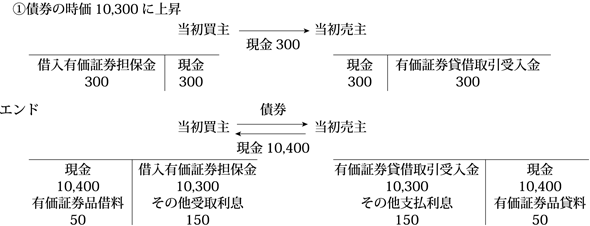国が本件課税処分をした背景として、表1にあるように、日本では売買形式だと有価証券取引税が課せられるのでそれを避けるために貸借形式のレポ取引が1996年に創設されたことにある。貸借形式だとレポ取引による利益は貸付金の利子に当たるので、源泉徴収義務が生じる。 国が本件課税処分をした背景として、表1にあるように、日本では売買形式だと有価証券取引税が課せられるのでそれを避けるために貸借形式のレポ取引が1996年に創設されたことにある。貸借形式だとレポ取引による利益は貸付金の利子に当たるので、源泉徴収義務が生じる。

 一方、国が負けた背景としては、海外では全て売買形式の統一契約書が使われており、本件取引もその統一契約書を用いていることにある。 一方、国が負けた背景としては、海外では全て売買形式の統一契約書が使われており、本件取引もその統一契約書を用いていることにある。

 ただし、会計基準では、買戻し条件売買は金融資産の譲渡に係る消滅の認識要件を満たさないために、売買取引とはされず、金融取引とされているために、会計の立場ではレポ取引による利益は貸付金の利子になる。 ただし、会計基準では、買戻し条件売買は金融資産の譲渡に係る消滅の認識要件を満たさないために、売買取引とはされず、金融取引とされているために、会計の立場ではレポ取引による利益は貸付金の利子になる。
 この件につき、判決はレポ取引の法的性質は会計基準には左右されないとしている。 この件につき、判決はレポ取引の法的性質は会計基準には左右されないとしている。 |
 |
〔2〕当事者の主張と裁判所の判断

 原告(=住友信託銀行)はそのケイマン支店を介し、子会社の米国住友信託銀行を代理人として、平成11年12月から平成13年6月まで海外の取引先との間で、MRAやGMRAという統一契約書を用いてレポ取引を行なった。 原告(=住友信託銀行)はそのケイマン支店を介し、子会社の米国住友信託銀行を代理人として、平成11年12月から平成13年6月まで海外の取引先との間で、MRAやGMRAという統一契約書を用いてレポ取引を行なった。

 原告は債券を買い戻す時に、当初の受領資金にレポ差額を上乗せして支払った。 原告は債券を買い戻す時に、当初の受領資金にレポ差額を上乗せして支払った。
 国はレポ差額が所得税法161条6号の「国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む)で当該業務に係るものの利子」に該当し、原告は本件レポ差額に係る所得税の源泉徴収義務があるとして、平成14年8月30日に約100億円の本件処分を行った。 国はレポ差額が所得税法161条6号の「国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む)で当該業務に係るものの利子」に該当し、原告は本件レポ差額に係る所得税の源泉徴収義務があるとして、平成14年8月30日に約100億円の本件処分を行った。

 原告は納付した金員の誤納金返還請求と本件処分の取消しを求める訴訟を提起した。 最大の争点は、レポ差額が貸付金(準ずるものを含む)の利子に該当するか否か、その前提として、受領資金が貸付金(準ずるものを含む)に該当するか否かである。 原告は納付した金員の誤納金返還請求と本件処分の取消しを求める訴訟を提起した。 最大の争点は、レポ差額が貸付金(準ずるものを含む)の利子に該当するか否か、その前提として、受領資金が貸付金(準ずるものを含む)に該当するか否かである。 |
 |
(1)貸付金と利子の意義

(国の主張)(地裁)
 貸付金は租税法の固有概念であり、私法上の金銭消費貸借に限られない。利子は一定期間の信用供与の対価である。 貸付金は租税法の固有概念であり、私法上の金銭消費貸借に限られない。利子は一定期間の信用供与の対価である。

(原告の主張)(地裁)
 貸付金は借用概念であり、私法上の金銭消費貸借を指す。利子は金銭消費貸借又はこれに類似している法律関係から生ずるものに限られる。 貸付金は借用概念であり、私法上の金銭消費貸借を指す。利子は金銭消費貸借又はこれに類似している法律関係から生ずるものに限られる。

(地裁の判断)
 貸付金は言葉の通常の用法に従って解釈すべきであり、社会一般では金銭消費貸借のみに用いられるとの共通認識はない。利子は元本債権から定期的に一定の割合で発生する法定果実である。 貸付金は言葉の通常の用法に従って解釈すべきであり、社会一般では金銭消費貸借のみに用いられるとの共通認識はない。利子は元本債権から定期的に一定の割合で発生する法定果実である。 |
 |
(2)本件レポ差額は利子であるか否か

(国の主張)(地裁)
 本件レポ取引は、債券保有者である原告が法形式は債券の売主となり(実質は債券を担保に供して)、資金を調達し、資金保有者が法形式は債券の買主となり(実質は債券を担保に取って)資金を提供し、利益を得ることにある。つまり、債券の買主が債券の売主である原告に対して一定期間信用を供与する取引であって、エンド取引の再売買代金の内、当初売買代金部分は貸付金で、残りの部分のレポ差額は利子である。 本件レポ取引は、債券保有者である原告が法形式は債券の売主となり(実質は債券を担保に供して)、資金を調達し、資金保有者が法形式は債券の買主となり(実質は債券を担保に取って)資金を提供し、利益を得ることにある。つまり、債券の買主が債券の売主である原告に対して一定期間信用を供与する取引であって、エンド取引の再売買代金の内、当初売買代金部分は貸付金で、残りの部分のレポ差額は利子である。

(原告の主張)(地裁)
 本件レポ取引は売買と再売買という法形式を取っており、金銭消費貸借の法形式ではないのだから、レポ差額は利子でない。 本件レポ取引は売買と再売買という法形式を取っており、金銭消費貸借の法形式ではないのだから、レポ差額は利子でない。

(地裁の判断)
 法形式及び経済的効果の両方を踏まえて、本件レポ取引の当初売買代金が金銭消費貸借契約における貸付債権とその性質、内容等がおおむね同様ないし類似するか否かを判断するべきである。 法形式及び経済的効果の両方を踏まえて、本件レポ取引の当初売買代金が金銭消費貸借契約における貸付債権とその性質、内容等がおおむね同様ないし類似するか否かを判断するべきである。

(高裁の判断)
 国のように専ら経済的効果のみに着目して、貸付金の解釈の範囲を広げることは租税法律主義の内容である租税要件明確主義に沿った解釈ということはできない。 国のように専ら経済的効果のみに着目して、貸付金の解釈の範囲を広げることは租税法律主義の内容である租税要件明確主義に沿った解釈ということはできない。 |
 |
(3)レポ差額の中身

(国の主張)(地裁)

レポ差額は
当初売買代金 × レポレート × スタート取引日からエンド取引日までの日数

360又は365 |
 |
(4)海外でのレポ取引の推移

(地裁の判断)
 アメリカにおいて、1982年に中堅証券会社が倒産し、その清算手続において、レポ取引(債券の売買と再売買とを内容とする契約)の法的性質が問題となった際、裁判所が担保付貸付けと判断したことから、当事者の債務不履行時に担保債券を処分することが困難になり、レポ取引の安全性に支障を生じた。 アメリカにおいて、1982年に中堅証券会社が倒産し、その清算手続において、レポ取引(債券の売買と再売買とを内容とする契約)の法的性質が問題となった際、裁判所が担保付貸付けと判断したことから、当事者の債務不履行時に担保債券を処分することが困難になり、レポ取引の安全性に支障を生じた。

 そこで、レポ取引に関与する市場関係者から、倒産隔離を念頭に、担保付貸付けと判断されないよう、統一的な標準契約書を作成する動きが起こり、1986年にMRAが作成され、その後改正等がされ、本件取引で使用されているMRAが1996年に作成された。 そこで、レポ取引に関与する市場関係者から、倒産隔離を念頭に、担保付貸付けと判断されないよう、統一的な標準契約書を作成する動きが起こり、1986年にMRAが作成され、その後改正等がされ、本件取引で使用されているMRAが1996年に作成された。

 イギリスにおいては、1992年にGMRAが作成され、1996年にイギリス国債のオープン・レポ・マーケット開設において導入された。イギリスにおいては、担保権の登録制度が採用されていることから、レポ取引の法的性質が担保付貸付けと評価されると、登録を経ていないことから、スタート取引時点において当該債券の完全な所有権移転がなされておらず、かつ担保権も設定されていないという疑義を生じさせることになるため、倒産隔離を確保するべく、レポ取引が法形式的に売買であることを明確にする必要があった。 イギリスにおいては、1992年にGMRAが作成され、1996年にイギリス国債のオープン・レポ・マーケット開設において導入された。イギリスにおいては、担保権の登録制度が採用されていることから、レポ取引の法的性質が担保付貸付けと評価されると、登録を経ていないことから、スタート取引時点において当該債券の完全な所有権移転がなされておらず、かつ担保権も設定されていないという疑義を生じさせることになるため、倒産隔離を確保するべく、レポ取引が法形式的に売買であることを明確にする必要があった。 |
 |
(5)基本契約書(MRA・GMRA)の内容

4条:マージンコール(値洗いのこと)
 有価証券の時価が売買代金と現時点のレポ差額の合計を下回る場合は、買主は売主に対して現金又は追加有価証券を支払うことを要求することができる。逆に、上回る場合は、売主は買主に対し要求することができる。 有価証券の時価が売買代金と現時点のレポ差額の合計を下回る場合は、買主は売主に対して現金又は追加有価証券を支払うことを要求することができる。逆に、上回る場合は、売主は買主に対し要求することができる。

(国の主張)
 買主は対象債券の価格変動によるリスクを負わず、エンド取引において再売買代金を確実に取得できるから、本件レポ取引は一定期間信用を供与する取引である。 買主は対象債券の価格変動によるリスクを負わず、エンド取引において再売買代金を確実に取得できるから、本件レポ取引は一定期間信用を供与する取引である。

(裁判所の判断)
 売主と買主の双方がエンド取引の不履行による損害を被らないために対象債券と再売買代金の対価的均衡を維持するためのものであり、売主及び買主双方がこの権利を有しているのに国はその一方のみを取りあげて強調しているにすぎない。 売主と買主の双方がエンド取引の不履行による損害を被らないために対象債券と再売買代金の対価的均衡を維持するためのものであり、売主及び買主双方がこの権利を有しているのに国はその一方のみを取りあげて強調しているにすぎない。

5条:収入金の支払い(利金のこと)
 売主は有価証券に関して支払われた収入金を受領することができる。買主は収入金を受領した場合、これを売主に返却する。ただし、マージンコール条項で売主が買主に支払う金額がある場合はこれと相殺できる。注 売主は有価証券に関して支払われた収入金を受領することができる。買主は収入金を受領した場合、これを売主に返却する。ただし、マージンコール条項で売主が買主に支払う金額がある場合はこれと相殺できる。注

(国の主張)
 売主には対象債券に生じた収入金を受領する権利が留保されており、買主に対象債券の完全な所有権が移転していない。 売主には対象債券に生じた収入金を受領する権利が留保されており、買主に対象債券の完全な所有権が移転していない。

(裁判所の判断)
 売主が対象債券について果実収取権を失うことを前提に、一定の要件の下で買主が売主に対し収入金を支払うことを定めたものであって、債券の所有権が買主に完全に移転していることと整合する。 売主が対象債券について果実収取権を失うことを前提に、一定の要件の下で買主が売主に対し収入金を支払うことを定めたものであって、債券の所有権が買主に完全に移転していることと整合する。

(注)収入金が支払われると債券の時価は下がると言われている。債券の時価が下がると買主は売主に対し下落分を要求できるので、相殺の場面が生じる。

6条:担保権(MRAのみ)
 当事者は本件取引が売買であることを意図している。にもかかわらず、貸付けとみなされた場合は、有価証券は担保として差入れたものとみなし、買主のために担保権が有価証券に設定されたものとみなす。 当事者は本件取引が売買であることを意図している。にもかかわらず、貸付けとみなされた場合は、有価証券は担保として差入れたものとみなし、買主のために担保権が有価証券に設定されたものとみなす。

(国の主張)
 本件レポ取引の本質が対象債券を担保とする与信行為であることを示している。 本件レポ取引の本質が対象債券を担保とする与信行為であることを示している。

(裁判所の判断)
 仮定的に設けられた条項であり、この条項を根拠としてレポ取引の法的性質に影響を与えるものではない。 仮定的に設けられた条項であり、この条項を根拠としてレポ取引の法的性質に影響を与えるものではない。

8条:購入有価証券の分別
 買主は購入有価証券を他の有価証券とは分別して占有する。債券に対する売主の全ての権利は購入時に買主に移転する。買主は購入有価証券を自由に処分することができる。ただし、エンド日での売主への売却義務は免除されない。 買主は購入有価証券を他の有価証券とは分別して占有する。債券に対する売主の全ての権利は購入時に買主に移転する。買主は購入有価証券を自由に処分することができる。ただし、エンド日での売主への売却義務は免除されない。

11条:債務不履行事由(一括精算)
 エンド日に売主が再売買代金を支払わない場合、買主は対象有価証券を売却して充当できる。売却代金が再売買代金に不足する場合、売主は不足分を買主に支払う責任を負う。 エンド日に売主が再売買代金を支払わない場合、買主は対象有価証券を売却して充当できる。売却代金が再売買代金に不足する場合、売主は不足分を買主に支払う責任を負う。

 エンド日に買主が対象有価証券を売主に引き渡さない場合、再売買代金を払わず代替有価証券を第3者から購入することができる。購入価格が再売買代金を上回った場合、買主は超過分を売主に支払う責任を負う。 エンド日に買主が対象有価証券を売主に引き渡さない場合、再売買代金を払わず代替有価証券を第3者から購入することができる。購入価格が再売買代金を上回った場合、買主は超過分を売主に支払う責任を負う。

 当事者間にある複数の契約関係の一つでも債務不履行事由が生じた場合、各取引のエンド日は全て到来したものとみなす。 当事者間にある複数の契約関係の一つでも債務不履行事由が生じた場合、各取引のエンド日は全て到来したものとみなす。

(国の主張)
 当事者の信用リスクを最小限に抑えることができるから、本件レポ取引は一定期間買主が売主に対し信用を供与する取引である。 当事者の信用リスクを最小限に抑えることができるから、本件レポ取引は一定期間買主が売主に対し信用を供与する取引である。

(裁判所の判断)
 当事者間に複数の契約関係がある場合に、リスクを回避するため各契約において債務不履行を原因とする期限の利益の喪失特約を定めることは特段不自然なことではない。 当事者間に複数の契約関係がある場合に、リスクを回避するため各契約において債務不履行を原因とする期限の利益の喪失特約を定めることは特段不自然なことではない。

 また、売主の債務不履行だけでなく、買主の債務不履行の場合の条項も置かれているから、買主から売主に対し信用を供与する取引だとして、その一方のみを強調することは相当とはいえない。 また、売主の債務不履行だけでなく、買主の債務不履行の場合の条項も置かれているから、買主から売主に対し信用を供与する取引だとして、その一方のみを強調することは相当とはいえない。 |
 |
(6)旧現先取引注(国は売買とする)との違い

(国の主張)(地裁)
 旧現先取引は期間中のリスク管理の仕組みや取引相手が債務不履行を起こした場合の取扱いが欠けているなどの点で本件レポ取引と内容や性質を異にしている。 旧現先取引は期間中のリスク管理の仕組みや取引相手が債務不履行を起こした場合の取扱いが欠けているなどの点で本件レポ取引と内容や性質を異にしている。

(原告の主張)(地裁)
 旧現先取引は、大蔵省証券局長通達により金銭の貸付又は貸借ではなく、売買として取扱うこととされ、その後有価証券取引税がスタートとエンドで課されていた。本件レポ取引は、旧現先取引と契約内容が酷似している。 旧現先取引は、大蔵省証券局長通達により金銭の貸付又は貸借ではなく、売買として取扱うこととされ、その後有価証券取引税がスタートとエンドで課されていた。本件レポ取引は、旧現先取引と契約内容が酷似している。

(注)旧現先取引
 現物買いの先物売りの略称で、将来の一定期日に、一定価額で反対売買を行うことをあらかじめ約束して債券の買付け又は売付けを行うもので、売戻条件付売買取引、又は買戻条件付売買取引をいう。 現物買いの先物売りの略称で、将来の一定期日に、一定価額で反対売買を行うことをあらかじめ約束して債券の買付け又は売付けを行うもので、売戻条件付売買取引、又は買戻条件付売買取引をいう。
差益は、

で求められており、レポ差額と、計算方法は類似している。国は有価証券取引税を課すために、売買とする一方で、有価証券取引税が廃止されるや売買ではなく、金銭の貸付けと主張している。 |
 |
(7)措置法42条の2(レポ差額は非課税)

(国の主張)(高裁)
 平成14年に設けられた措置法42条の2は本件レポ取引から生じるレポ差額が貸付金の利子であることを前提にして、特例として所得税を課さないことを定めた創設的な規定である。 平成14年に設けられた措置法42条の2は本件レポ取引から生じるレポ差額が貸付金の利子であることを前提にして、特例として所得税を課さないことを定めた創設的な規定である。

(原告の主張)(高裁)
 本件レポ取引が行なわれた当時には措置法42条の2はないのだから、本件課税処分の根拠にはなりえない。又措置法42条の2は課税要件を定めた規定ではなく、本件レポ差額が貸付金の利子に当たるか否かは、所得税法161条6項の解釈に委ねられていると解すべきである。 本件レポ取引が行なわれた当時には措置法42条の2はないのだから、本件課税処分の根拠にはなりえない。又措置法42条の2は課税要件を定めた規定ではなく、本件レポ差額が貸付金の利子に当たるか否かは、所得税法161条6項の解釈に委ねられていると解すべきである。

(高裁の判断)
 本件レポ差額が貸付金の利子であるか否かは課税要件を定めた所得税法161条6号自体の解釈が重視されるべきであり、措置法42条の2はその解釈の根拠とはなりえない。 本件レポ差額が貸付金の利子であるか否かは課税要件を定めた所得税法161条6号自体の解釈が重視されるべきであり、措置法42条の2はその解釈の根拠とはなりえない。

(注)平成21年に所得税法161条6号が改正され、レポ差額は貸付金の利子とされた。 |
 |
(8)会計基準(レポ取引は金融取引)

(国の主張)(高裁)
 企業会計審議会は平成11年1月22日に「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」でレポ取引は買戻す合意があるため、譲渡資産の支配が移転しているとは認められず、売買取引ではなく金融取引として処理する必要があるとしている。 企業会計審議会は平成11年1月22日に「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」でレポ取引は買戻す合意があるため、譲渡資産の支配が移転しているとは認められず、売買取引ではなく金融取引として処理する必要があるとしている。

 日本公認会計士協会は平成12年1月31日に「金融商品会計に関する実務指針」で、レポ取引は金融取引処理をする。債券の売主は借入れを行ない、担保として有価証券を差し入れ、債券の買主は貸付けを行い、有価証券を担保受入金融資産として受領するとしている。 日本公認会計士協会は平成12年1月31日に「金融商品会計に関する実務指針」で、レポ取引は金融取引処理をする。債券の売主は借入れを行ない、担保として有価証券を差し入れ、債券の買主は貸付けを行い、有価証券を担保受入金融資産として受領するとしている。

 原告は本件レポ取引でスタート取引で受領した金員を「その他負債」の科目で仕訳処理し、エンド取引で支払ったレポ差額の金員を「その他の支払利息」の科目で仕訳処理している。 原告は本件レポ取引でスタート取引で受領した金員を「その他負債」の科目で仕訳処理し、エンド取引で支払ったレポ差額の金員を「その他の支払利息」の科目で仕訳処理している。

 レポ取引の専門家は、MRAやGMRAに基づくレポ取引について、経済的には信用供与に伴う金融取引としての性格を有していると指摘している。 レポ取引の専門家は、MRAやGMRAに基づくレポ取引について、経済的には信用供与に伴う金融取引としての性格を有していると指摘している。

(原告の主張)(高裁)
 本件レポ取引が行なわれた期間中に取扱いに変更があった会計処理上の扱いを、本件レポ差額の課税根拠として持ち出すことは何らの論理性もない。 本件レポ取引が行なわれた期間中に取扱いに変更があった会計処理上の扱いを、本件レポ差額の課税根拠として持ち出すことは何らの論理性もない。

(高裁の判断)
 レポ取引をどのような勘定科目で計上するかは専ら会計基準により定まる問題である。会計基準においては会社法(本件取引時は商法)等の法律上の概念は考慮されてはいるものの、同一ではなく、別次元のものであって、企業会計上の取扱い等を根拠に、法律上の概念について法的性質を決定することは相当とはいえない。 レポ取引をどのような勘定科目で計上するかは専ら会計基準により定まる問題である。会計基準においては会社法(本件取引時は商法)等の法律上の概念は考慮されてはいるものの、同一ではなく、別次元のものであって、企業会計上の取扱い等を根拠に、法律上の概念について法的性質を決定することは相当とはいえない。 |
 |
(9)所得税法施行令283条1項(6カ月以下は非課税)

(国の主張)(地裁)
 債権の履行期間が発生から6カ月を超えないものの利子は技術的な不都合があるために源泉徴収の対象から除外されたにすぎず、当該債権が貸付金であることに変わりはない。 債権の履行期間が発生から6カ月を超えないものの利子は技術的な不都合があるために源泉徴収の対象から除外されたにすぎず、当該債権が貸付金であることに変わりはない。

(原告の主張)(地裁)
 債権の履行期間が発生から6カ月を超えないものについては利子ではないことを明らかにしたものである。本件レポ取引のスタート取引からエンド取引までの期間はいずれも6カ月以下であるから利子ではないことになる。 債権の履行期間が発生から6カ月を超えないものについては利子ではないことを明らかにしたものである。本件レポ取引のスタート取引からエンド取引までの期間はいずれも6カ月以下であるから利子ではないことになる。

(高裁の判断)
 債権の履行期間が発生から6カ月を超えないものについては、所得税法161条6号の貸付金(これに準ずるものを含む)の利子から除外していることを明記しているから、仮に国の主張するように所得税法161条6号が本件レポ取引に適用されるのであれば、所得税法施行令283条1項もレポ取引に適用されることとなり、スタート取引からエンド取引までの期間が6カ月を超えていない本件レポ取引については、本件レポ差額は源泉徴収義務の対象とならないことになる。 債権の履行期間が発生から6カ月を超えないものについては、所得税法161条6号の貸付金(これに準ずるものを含む)の利子から除外していることを明記しているから、仮に国の主張するように所得税法161条6号が本件レポ取引に適用されるのであれば、所得税法施行令283条1項もレポ取引に適用されることとなり、スタート取引からエンド取引までの期間が6カ月を超えていない本件レポ取引については、本件レポ差額は源泉徴収義務の対象とならないことになる。 |
 |
(10)結論

(地裁の結論)
 原告が使用したMRAやGMRAの契約は倒産隔離を果たすために、契約条項において売買及び再売買により構成されることを明確に定めたものであって、金融的取引の側面が存在し、それを示唆するかのような条項の存在によっても、その法的性質を変容させるまでのものとはいえない。 原告が使用したMRAやGMRAの契約は倒産隔離を果たすために、契約条項において売買及び再売買により構成されることを明確に定めたものであって、金融的取引の側面が存在し、それを示唆するかのような条項の存在によっても、その法的性質を変容させるまでのものとはいえない。

 したがって、本件契約に基づく本件レポ取引は、売買・再売買を1つの契約で実行する複合的な性格を有する契約であると解するのが相当である。 したがって、本件契約に基づく本件レポ取引は、売買・再売買を1つの契約で実行する複合的な性格を有する契約であると解するのが相当である。

(高裁の結論)
 レポ取引には資金調達的な面があることは確かであるが、債券の調達に資する面もあり、顧客に対して、先売りを行った債券ディラーが取引の決済日までに債券を調達するために、他者から債券を一時的に購入することにも使われる注から、金融機能的側面とともに、債券売買市場の流動性の確保も経済的機能としては考慮されるべきである。これらを売買及び再売買という法律構成の下で実現しようとしているのだから、私的自治の作用する取引関係において当事者が上記のような法律形態を選択して取引関係に入り、その法律形態に特段不合理なものがない以上、その契約関係を基本に解釈すべきものである。 レポ取引には資金調達的な面があることは確かであるが、債券の調達に資する面もあり、顧客に対して、先売りを行った債券ディラーが取引の決済日までに債券を調達するために、他者から債券を一時的に購入することにも使われる注から、金融機能的側面とともに、債券売買市場の流動性の確保も経済的機能としては考慮されるべきである。これらを売買及び再売買という法律構成の下で実現しようとしているのだから、私的自治の作用する取引関係において当事者が上記のような法律形態を選択して取引関係に入り、その法律形態に特段不合理なものがない以上、その契約関係を基本に解釈すべきものである。

 このような法律形態を素直にとらえることなく、レポ取引の持つ金融取引的側面のみを強調し、専らこの観点からスタート取引の売買代金を貸付金と解することは無理がある。 このような法律形態を素直にとらえることなく、レポ取引の持つ金融取引的側面のみを強調し、専らこの観点からスタート取引の売買代金を貸付金と解することは無理がある。
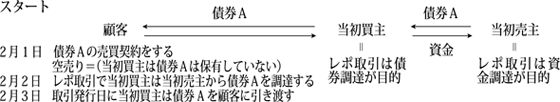
 レポ取引が債券Aを担保にした貸付けならば、当初買主は債券Aを顧客に売却すると担保保存義務違反に問われる。これに対し、レポ取引を売買・再売買の法形式にすれば、当初買主は債券Aを自由に処分できるので、空売りした債券に使用できる。 レポ取引が債券Aを担保にした貸付けならば、当初買主は債券Aを顧客に売却すると担保保存義務違反に問われる。これに対し、レポ取引を売買・再売買の法形式にすれば、当初買主は債券Aを自由に処分できるので、空売りした債券に使用できる。 |
 |
〔3〕検討

(1)金融取引による処理

 金融商品会計基準によれば、レポ取引は当初売主が譲渡した債券を債券の満期日前に買い戻す権利及び義務を有しているので、金融資産の消滅の認識要件を満たさず、債券の契約上の権利は当初買主に移転しないものとされ、金融取引として処理することとされている。 金融商品会計基準によれば、レポ取引は当初売主が譲渡した債券を債券の満期日前に買い戻す権利及び義務を有しているので、金融資産の消滅の認識要件を満たさず、債券の契約上の権利は当初買主に移転しないものとされ、金融取引として処理することとされている。

 諸外国でもレポ取引は当初売主は「買戻条件付売却有価証券」という科目で負債計上、当初買主は「売戻条件付購入有価証券」という科目で資産計上し、金融取引として処理されている。 諸外国でもレポ取引は当初売主は「買戻条件付売却有価証券」という科目で負債計上、当初買主は「売戻条件付購入有価証券」という科目で資産計上し、金融取引として処理されている。
 仮設例により、金融取引で処理すると次のようになる。 仮設例により、金融取引で処理すると次のようになる。

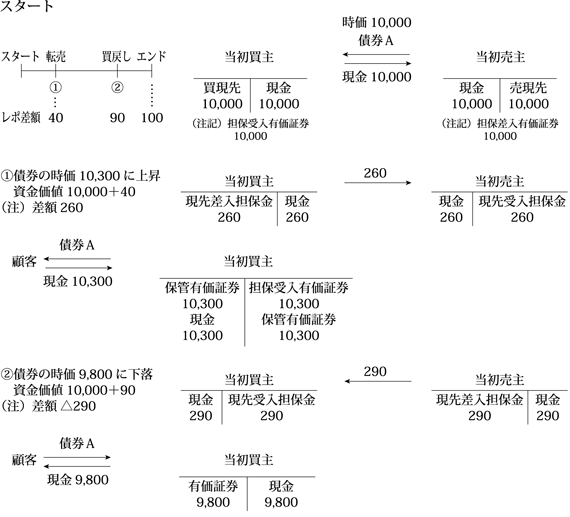
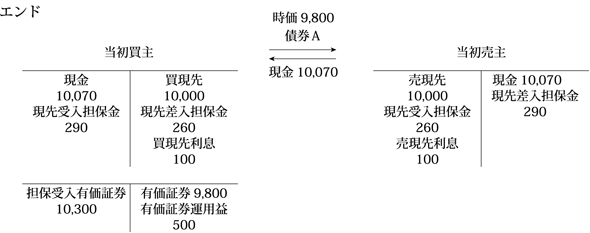

(注)マージンコール
 債券時価の変動による信用リスクを軽減するために設けられた制度で、債券の時価が上昇した場合、当初売主は上昇分に見合う一定額を当初買主に請求する権利を有し、逆に債券の時価が下落した場合、当初買主は下落分に見合う一定額を当初売主に請求する権利を有する。 債券時価の変動による信用リスクを軽減するために設けられた制度で、債券の時価が上昇した場合、当初売主は上昇分に見合う一定額を当初買主に請求する権利を有し、逆に債券の時価が下落した場合、当初買主は下落分に見合う一定額を当初売主に請求する権利を有する。

 債券を担保にした貸付けとの違いは、担保債券の時価が下落した場合、当初買主である貸主が担保追加を当初売主である借主に要求することと同じであるが、担保債券の時価が上昇した場合、借主が貸主に追加貸付けを要求することはない点である。 債券を担保にした貸付けとの違いは、担保債券の時価が下落した場合、当初買主である貸主が担保追加を当初売主である借主に要求することと同じであるが、担保債券の時価が上昇した場合、借主が貸主に追加貸付けを要求することはない点である。

 この目的は、エンドで当初買主が当初売主に債券を引き渡せない債務不履行が生じた場合に当初売主は上昇した時価で債券を他者から入手せざるを得なくなるが、上昇分に見合う一定額を当初買主から前もって入手してその損失をなくすことである。 この目的は、エンドで当初買主が当初売主に債券を引き渡せない債務不履行が生じた場合に当初売主は上昇した時価で債券を他者から入手せざるを得なくなるが、上昇分に見合う一定額を当初買主から前もって入手してその損失をなくすことである。

 つまり、貸付けでは、貸主である当初買主のリスク保護しか考えないが、レポ取引では当初買主と当初売主の両方のリスク保護を考えている。 つまり、貸付けでは、貸主である当初買主のリスク保護しか考えないが、レポ取引では当初買主と当初売主の両方のリスク保護を考えている。 |
 |
(2)売買取引による処理[(1)の設例と同じ]

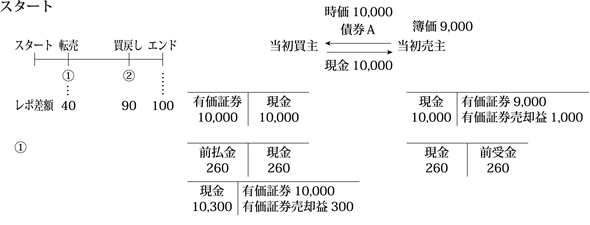

 エンドでの再売買代金は10100とスタートで決まっているので、エンドでの債券時価との差額処理が必要となり、当初買主は受贈益、当初売主は寄付金を各々計上する。 エンドでの再売買代金は10100とスタートで決まっているので、エンドでの債券時価との差額処理が必要となり、当初買主は受贈益、当初売主は寄付金を各々計上する。
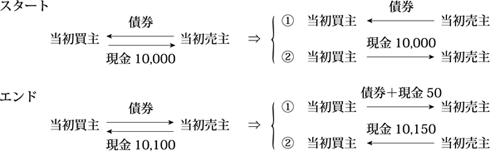
 レポ取引は経済的実質で見れば、 レポ取引は経済的実質で見れば、 現金担保付債券貸借取引と 現金担保付債券貸借取引と  債券担保付金銭消費貸借取引に分解される。 債券担保付金銭消費貸借取引に分解される。

  の債券貸借料率を0.5%、 の債券貸借料率を0.5%、 の金利を1.5%とすれば、レポレートは1.5%ー 0.5%= 1.0%となる。この利率での取引期間での値を貸借料を50、利息を150とすれば、レポ差額は100となる。 の金利を1.5%とすれば、レポレートは1.5%ー 0.5%= 1.0%となる。この利率での取引期間での値を貸借料を50、利息を150とすれば、レポ差額は100となる。

 これを本件レポ取引に当てはめれば、国は100に対する源泉徴収義務を原告である当初売主に課したが、1.50が本来は源泉徴収の対象になっている。 これを本件レポ取引に当てはめれば、国は100に対する源泉徴収義務を原告である当初売主に課したが、1.50が本来は源泉徴収の対象になっている。
 1996年に始まった日本版レポの会計処理はこれでなされていた。 1996年に始まった日本版レポの会計処理はこれでなされていた。

(1)の設例を用いて処理すると次のようになる

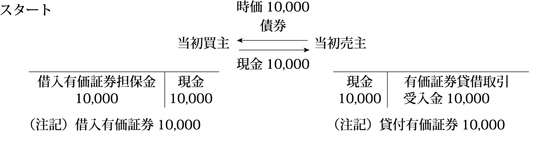
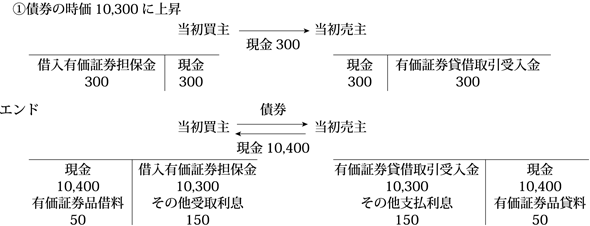 |
 |
(4)まとめ

 国は原告が選択した売買という法形式を経済的実質の観点から貸付けという法形式に引き直して課税したわけだが、裁判所は当事者が選択した売買という法形式に格別に不合理な点がないかぎり、その選択した法形式を尊重すべきだと判決した。 国は原告が選択した売買という法形式を経済的実質の観点から貸付けという法形式に引き直して課税したわけだが、裁判所は当事者が選択した売買という法形式に格別に不合理な点がないかぎり、その選択した法形式を尊重すべきだと判決した。

 この考えは岩瀬事件等の近時の判例の流れに沿うものである。ただし、本件の場合次の点で違いがある。 この考えは岩瀬事件等の近時の判例の流れに沿うものである。ただし、本件の場合次の点で違いがある。
 それは会計基準と当事者の選択した法形式が違う場合には当事者の選択した法形式を尊重すべきだとしたことである。 それは会計基準と当事者の選択した法形式が違う場合には当事者の選択した法形式を尊重すべきだとしたことである。

 著名な法律家の言によると 著名な法律家の言によると  取引の法律上の性格付けを会計原則で変更することはできない。 取引の法律上の性格付けを会計原則で変更することはできない。 課税所得算定の根幹部分が会計原則に委ねられてしまえば、租税法律主義に反する。 課税所得算定の根幹部分が会計原則に委ねられてしまえば、租税法律主義に反する。 会計原則は私法によりもたらされた経済的効果を記述する技術でしかない。 会計原則は私法によりもたらされた経済的効果を記述する技術でしかない。

 本件で判決と会計基準で、結論が違うのは前者はスタートの売買とエンドの再売買を別々の法形式としてとらえるのに対し、後者はスタートからエンドまでを一つの会計事象としてとらえているためである。 本件で判決と会計基準で、結論が違うのは前者はスタートの売買とエンドの再売買を別々の法形式としてとらえるのに対し、後者はスタートからエンドまでを一つの会計事象としてとらえているためである。

 判決は買主が債券を自由に処分できるのは売買だからであり、担保ではできないというが、この点については債券の消費貸借でも自由に処分できる。この考え方が(3)の貸借レポである。ただし、本件では債券の貸借料率が契約書等にでないように工夫されていた。レポレートという言葉の裏に隠されていた。 判決は買主が債券を自由に処分できるのは売買だからであり、担保ではできないというが、この点については債券の消費貸借でも自由に処分できる。この考え方が(3)の貸借レポである。ただし、本件では債券の貸借料率が契約書等にでないように工夫されていた。レポレートという言葉の裏に隠されていた。
(レポレート=金利ー貸借料率)

 判決に影響を与えた要因としてつ次の2点が考えられる。 判決に影響を与えた要因としてつ次の2点が考えられる。
 第一は欧米では売買形式のレポ取引が大量に行われ、そこでは源泉徴収はされておらず、本件取引もその中でのアメリカで行われた取引であるということ。 第一は欧米では売買形式のレポ取引が大量に行われ、そこでは源泉徴収はされておらず、本件取引もその中でのアメリカで行われた取引であるということ。

 第二は旧現先取引について売買だとして有価証券取引税を課したが、本件取引と旧現先取引とはリスク管理等の違いはあるものの売買・再売買という法形式は共通している。それなのに、国が本件取引を売買ではないと主張していることに対して不信感をいだいたということ。 第二は旧現先取引について売買だとして有価証券取引税を課したが、本件取引と旧現先取引とはリスク管理等の違いはあるものの売買・再売買という法形式は共通している。それなのに、国が本件取引を売買ではないと主張していることに対して不信感をいだいたということ。 |
(ふね・しげお) |