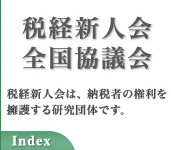消費税増税派にとっての最大のネックが消費税の逆進性である。消費税は最終的には消費者が負担する税であり、課税対象があらゆる生活必需品に及んでいる為、所得の低い人ほど負担割合が高くなる。高額所得者は稼得した所得をすべて消費することはない。所得の多くは預貯金や土地、株式等の購入へ支出される。土地や株式等の売買には消費税負担は無い。利子、配当等の収入についても消費税負担は無い。投資活動には消費税負担は無いのである。 消費税増税派にとっての最大のネックが消費税の逆進性である。消費税は最終的には消費者が負担する税であり、課税対象があらゆる生活必需品に及んでいる為、所得の低い人ほど負担割合が高くなる。高額所得者は稼得した所得をすべて消費することはない。所得の多くは預貯金や土地、株式等の購入へ支出される。土地や株式等の売買には消費税負担は無い。利子、配当等の収入についても消費税負担は無い。投資活動には消費税負担は無いのである。

 「生活費に消費税をかけるな!せめて食料品は非課税に!」は庶民の心からの願いである。消費税の増税に反対する運動のスローガンでもある。「大綱」も消費税の逆進性を認めざるを得ない。しかし、軽減税率については、「非常に複雑な制度を生むこととなる可能性がある」として否定している。「大綱」は、逆進性対策は「給付付き税額控除」で行うとしている。 「生活費に消費税をかけるな!せめて食料品は非課税に!」は庶民の心からの願いである。消費税の増税に反対する運動のスローガンでもある。「大綱」も消費税の逆進性を認めざるを得ない。しかし、軽減税率については、「非常に複雑な制度を生むこととなる可能性がある」として否定している。「大綱」は、逆進性対策は「給付付き税額控除」で行うとしている。

 「給付付き税額控除」とはどの様な仕組みか。「アクションプログラム」によると「給付付き消費税額控除」は、「家計調査などの客観的な統計に基づき、年間の基礎的な消費支出に係る消費税相当額を一律に税額控除し、控除しきれない部分については給付する」制度である。これにより逆進性を緩和し、最低限の生活にかかる消費税を免除するとしている。はたしてどうであろうか。以下 「給付付き税額控除」とはどの様な仕組みか。「アクションプログラム」によると「給付付き消費税額控除」は、「家計調査などの客観的な統計に基づき、年間の基礎的な消費支出に係る消費税相当額を一律に税額控除し、控除しきれない部分については給付する」制度である。これにより逆進性を緩和し、最低限の生活にかかる消費税を免除するとしている。はたしてどうであろうか。以下  行政費用の問題、 行政費用の問題、 民主主義、人権の問題、 民主主義、人権の問題、 経済効果の問題、 経済効果の問題、 逆進性緩和の効果の問題、 逆進性緩和の効果の問題、 調査と罰則の問題の5点についてみてみたい。 調査と罰則の問題の5点についてみてみたい。 |
 |
(1)行政費用について

 税、社会保障をめぐる国家制度のあり方については、「大綱」は「納税環境整備」で方向性を示している。 税、社会保障をめぐる国家制度のあり方については、「大綱」は「納税環境整備」で方向性を示している。

 「大綱」は「納税環境整備」について5つの方向性とそれを検討するプロジェクトチームの設置をあげている。5つの方向性とは、 「大綱」は「納税環境整備」について5つの方向性とそれを検討するプロジェクトチームの設置をあげている。5つの方向性とは、 納税者権利憲章の制定、 納税者権利憲章の制定、 国税不服審判所の改革、 国税不服審判所の改革、 社会保障、税共通の番号制度導入、 社会保障、税共通の番号制度導入、 歳入庁の設置、 歳入庁の設置、 罰則の適正化、である。 罰則の適正化、である。 、 、 については、自民党政権時代より、その必要性や問題性が国民の運動によって指摘されてきたものである。納税者の税制上の権利拡大につながる方向性と言える。「大綱」は、この権利拡大と引き換えに、 については、自民党政権時代より、その必要性や問題性が国民の運動によって指摘されてきたものである。納税者の税制上の権利拡大につながる方向性と言える。「大綱」は、この権利拡大と引き換えに、 、 、 、 、 を狙っている。納税者の管理、制裁の機構づくりの方向性を示している。 を狙っている。納税者の管理、制裁の機構づくりの方向性を示している。

 「罰則の適正化」では、「義務を適正に履行しない納税者に対しては厳格かつ的確に対処する必要」があるとして、罰則強化を打ち出している。権利も認めるが、義務違反に対する制裁も厳しくするということか? 「罰則の適正化」では、「義務を適正に履行しない納税者に対しては厳格かつ的確に対処する必要」があるとして、罰則強化を打ち出している。権利も認めるが、義務違反に対する制裁も厳しくするということか?

 「歳入庁の設置」は、「税と社会保険料の賦課徴収の一元化」を目的としており、「地方税等の徴収事務の受託」も行うのである。税、社会保険料、地方税等の賦課徴収の権限をもつ「スーパー税務調査官」の出現もありうる。権力の乱用が危惧される。 「歳入庁の設置」は、「税と社会保険料の賦課徴収の一元化」を目的としており、「地方税等の徴収事務の受託」も行うのである。税、社会保険料、地方税等の賦課徴収の権限をもつ「スーパー税務調査官」の出現もありうる。権力の乱用が危惧される。

 社会保障、税共通の番号制度は、「社会保障制度の効率化」と「所得把握体制」づくりをめざすものである。その実施機関が歳入庁であり、厳正化のための罰則強化でもある。 社会保障、税共通の番号制度は、「社会保障制度の効率化」と「所得把握体制」づくりをめざすものである。その実施機関が歳入庁であり、厳正化のための罰則強化でもある。

 「給付付き税額控除」制度は、共通番号制の導入とも相まって、巨大な国民監視、管理、調査、制裁機構の構築と表裏一体のものと言える。巨大な行政費用を伴うものである。 「給付付き税額控除」制度は、共通番号制の導入とも相まって、巨大な国民監視、管理、調査、制裁機構の構築と表裏一体のものと言える。巨大な行政費用を伴うものである。

 これに対して、軽減税率の場合は、事業者に事務上の負担を強いることはあるが、特段の行政費用は必要ない。 これに対して、軽減税率の場合は、事業者に事務上の負担を強いることはあるが、特段の行政費用は必要ない。 |
 |
(2)民主主義、人権問題について

 税や社会保障については、すでに行政別、目的別の番号制度がある。共通番号制度は、目的や省庁横断的番号制度のことである。共通番号として、「住民基本台帳ネットワーク」が想定されている。共通番号は、税、医療、介護、年金、教育などの公的分野だけでなく、金融取引、生保損保などの保険、運輸、通信関係など生活のあらゆる分野で使用される可能性がある。共通番号なしには仕事にもつけない、生活するのも困難となる可能性がある。 税や社会保障については、すでに行政別、目的別の番号制度がある。共通番号制度は、目的や省庁横断的番号制度のことである。共通番号として、「住民基本台帳ネットワーク」が想定されている。共通番号は、税、医療、介護、年金、教育などの公的分野だけでなく、金融取引、生保損保などの保険、運輸、通信関係など生活のあらゆる分野で使用される可能性がある。共通番号なしには仕事にもつけない、生活するのも困難となる可能性がある。

 国家権力による、国民一人一人を管理、監視、調査、取締、制裁する巨大機構の出現である。 歳入庁には、共通番号による「個人口座」が設置される。共通番号で、国保料、年金掛金、学校給食等々の滞納、未納がないかチェックする。滞納、未納があれば給付との相殺、「給付」の保留、打ち切りとなる。「給付」の保留や打切りは、国民に対する「兵糧攻め」とも言える。 国家権力による、国民一人一人を管理、監視、調査、取締、制裁する巨大機構の出現である。 歳入庁には、共通番号による「個人口座」が設置される。共通番号で、国保料、年金掛金、学校給食等々の滞納、未納がないかチェックする。滞納、未納があれば給付との相殺、「給付」の保留、打ち切りとなる。「給付」の保留や打切りは、国民に対する「兵糧攻め」とも言える。

 プライバシー権の侵害、生活権、生存権の侵害、管理される情報の安全性の問題など、重大な人権侵害の可能性を含んでいる。又、調査権、制裁件などが行政権力により乱用される可能性もある。国民の視点からは、わずかな「利便性」と引換えに失うものは、あまりにも大きすぎる。 プライバシー権の侵害、生活権、生存権の侵害、管理される情報の安全性の問題など、重大な人権侵害の可能性を含んでいる。又、調査権、制裁件などが行政権力により乱用される可能性もある。国民の視点からは、わずかな「利便性」と引換えに失うものは、あまりにも大きすぎる。
 これに対して、軽減税率は全く問題が生じない。 これに対して、軽減税率は全く問題が生じない。 |
 |
(3)経済的効果について

 現在のデフレ不況の原因が、消費不足による不況であることは多くの論者の示すところである。食料品に対する非課税や生活必需品の軽減税率は、日々の買い物でその恩恵を実感できる。消費を促進する効果もあり、不況対策としても有効である。 現在のデフレ不況の原因が、消費不足による不況であることは多くの論者の示すところである。食料品に対する非課税や生活必需品の軽減税率は、日々の買い物でその恩恵を実感できる。消費を促進する効果もあり、不況対策としても有効である。

 これに対して、「給付付き税額控除」は、申告、申請が必要であり、手続きが煩雑である。不正や誤りを防ぐための事務作業も必要であり、納税者への給付は事後的となる。又、控除税額は、家計調査などの客観的統計に基づいて国によって決定されるが、「最低限の生活」をどう考えるかは国のさじ加減となる可能性がある。 これに対して、「給付付き税額控除」は、申告、申請が必要であり、手続きが煩雑である。不正や誤りを防ぐための事務作業も必要であり、納税者への給付は事後的となる。又、控除税額は、家計調査などの客観的統計に基づいて国によって決定されるが、「最低限の生活」をどう考えるかは国のさじ加減となる可能性がある。 |
 |
(4)逆進性の緩和について

 非課税、軽減税率は、老若男女すべての国民が買い物のたびにその恩恵を受ける。子供達も。何ら手続きは必要ない。共通番号を示す必要もない。逆進性緩和は、文字通り完全に実施されるのである。 非課税、軽減税率は、老若男女すべての国民が買い物のたびにその恩恵を受ける。子供達も。何ら手続きは必要ない。共通番号を示す必要もない。逆進性緩和は、文字通り完全に実施されるのである。

 これに対し「給付付き税額控除」は、申告・申請が必要である。申告、申請をした人が恩恵を受ける。原則として成人である。何らかの事情で申告できない人は対象外となる。申告できない人に経済的弱者が多いのである。 これに対し「給付付き税額控除」は、申告・申請が必要である。申告、申請をした人が恩恵を受ける。原則として成人である。何らかの事情で申告できない人は対象外となる。申告できない人に経済的弱者が多いのである。

 破産・多重債務・失業・家庭内暴力などの理由で住所を明らかにできない人など給付を必要とする人が給付を受けられない可能性が大きいと言える。真の逆進性の緩和とはならない。 破産・多重債務・失業・家庭内暴力などの理由で住所を明らかにできない人など給付を必要とする人が給付を受けられない可能性が大きいと言える。真の逆進性の緩和とはならない。 |
 |
(5)調査と罰則について

 申告、申請には、過誤還付が必ず発生する。又、不正還付も出てくる。その為に共通番号による管理体制とセットとなっている。しかし、共通番号は万能ではない。調査、取締の強化、罰則による制裁の強化が必要となる。 申告、申請には、過誤還付が必ず発生する。又、不正還付も出てくる。その為に共通番号による管理体制とセットとなっている。しかし、共通番号は万能ではない。調査、取締の強化、罰則による制裁の強化が必要となる。

 「給付付き税額控除」には、調査と罰則が必須条件となる。その為の人件費、物件費、組織体制が必要となる。行政費用も増える。 「給付付き税額控除」には、調査と罰則が必須条件となる。その為の人件費、物件費、組織体制が必要となる。行政費用も増える。

 これに対して、非課税、軽減税率には、過誤還付、不正還付など有り様がない。 これに対して、非課税、軽減税率には、過誤還付、不正還付など有り様がない。

 以上5点にわたって「給付付き税額控除」と非課税、軽減税率とを比較してきた。(表1参照)「大綱」の言う、軽減税率は「非常に複雑な制度を生むこととなる可能性がある」などとの言は欺瞞であることは明らかである。又、逆進性対策としての「給付付き税額控除」が真の逆進性対策ではない。その本当の目的は、共通番号制の導入を手掛かりに、国民一人一人を管理、監視、調査、取締、制裁する巨大な権力機構づくりであることは明らかである。ここに「給付付き税額控除」の真の欺瞞性がある。 以上5点にわたって「給付付き税額控除」と非課税、軽減税率とを比較してきた。(表1参照)「大綱」の言う、軽減税率は「非常に複雑な制度を生むこととなる可能性がある」などとの言は欺瞞であることは明らかである。又、逆進性対策としての「給付付き税額控除」が真の逆進性対策ではない。その本当の目的は、共通番号制の導入を手掛かりに、国民一人一人を管理、監視、調査、取締、制裁する巨大な権力機構づくりであることは明らかである。ここに「給付付き税額控除」の真の欺瞞性がある。 |
 「アクションプログラム」や「大綱」では、消費税を「基幹税」と位置付けている。税収として「消費税は景気に左右されない税目」である。税収の安定性を理由としている。 「アクションプログラム」や「大綱」では、消費税を「基幹税」と位置付けている。税収として「消費税は景気に左右されない税目」である。税収の安定性を理由としている。

 消費税に対する国民の厳しい批判も意識している。「使途の明確化」「逆進性対策」「課税の一層の適正化」を検討課題としている。 消費税に対する国民の厳しい批判も意識している。「使途の明確化」「逆進性対策」「課税の一層の適正化」を検討課題としている。

 「使途の明確化」については、消費税を「社会保障目的税」化の方向で。「逆進性対策」については「給付付き税額控除」制度の方向で。 「使途の明確化」については、消費税を「社会保障目的税」化の方向で。「逆進性対策」については「給付付き税額控除」制度の方向で。

「課税の一層の適正化」については、「共通番号制度」「インボイス制度」「歳入庁の創設」「罰則の強化」などの納税環境整備によって国民の批判をかわし、「基幹税」にふさわしい税目にしようとしている。しかし、生活費に対する課税である消費税が「基幹税」たることを、国民が許すことはない。税収の安定性が「基幹税」の要件ではない。そもそも「租税」の対象となる税源をどこに求めるか、現行消費税の実態、問題点はどこにあるかを検討する中で、「基幹税」とは何かを考える。 |
 |
(1)社会的剰余等が本来の税源

 社会的視点で見た時、税負担は社会的剰余に求められるべきである。資本主義社会では、社会的剰余は個人や企業に帰属する。会計上の「利益」である。社会的剰余は、現象としては、利益だけでなく、利子、配当、地代、家賃、役員給与などの形態をとる。 社会的視点で見た時、税負担は社会的剰余に求められるべきである。資本主義社会では、社会的剰余は個人や企業に帰属する。会計上の「利益」である。社会的剰余は、現象としては、利益だけでなく、利子、配当、地代、家賃、役員給与などの形態をとる。

 社会が継続的に活動していく為には、その成員一人一人の飲食、住居、衣服が満たされている必要がある。いかなる時代であれ生活が充足されなければ社会は成り立たないのである。これが社会の基礎をなす。人間はその社会活動の中でこの社会的基礎を超える剰余を生みだす。自らの再生産(生活)に必要なるもの以上を生みだす。これが社会的剰余である。社会的剰余が誰に帰属するのか、どの様な方法で蓄積、分配されるのかで社会のあり方が異なる。 社会が継続的に活動していく為には、その成員一人一人の飲食、住居、衣服が満たされている必要がある。いかなる時代であれ生活が充足されなければ社会は成り立たないのである。これが社会の基礎をなす。人間はその社会活動の中でこの社会的基礎を超える剰余を生みだす。自らの再生産(生活)に必要なるもの以上を生みだす。これが社会的剰余である。社会的剰余が誰に帰属するのか、どの様な方法で蓄積、分配されるのかで社会のあり方が異なる。

 生活費をまかなう社会的基礎部分は、労働者の賃金、給与として、あるいは零細事業者の事業所得などとして分配される。社会的剰余は、資本の所有者である個人や企業に帰属する。しかし、均等に平等に配分されることは無い。貧富の差を生みだす。これを是正するために財政による「所得の再配分」が必要となる。その為に社会的剰余に課税するのである。課税の対象たる「税源」は社会的剰余に求めるべきである。現代社会では社会的基礎をなす生活費も社会的剰余も「所得」として現象する。社会的剰余たる「所得」への課税こそが現代税法の使命であると考える。「所得」を課税対象とする所得税、法人税こそが「基幹税」にふさわしいと言える。生活費課税たる消費税は「基幹税」などではありえない。消費税は「利益」に税負担をもとめることはない。消費税「基幹税」論は、大企業、大資産家への利益を擁護する理論である。 生活費をまかなう社会的基礎部分は、労働者の賃金、給与として、あるいは零細事業者の事業所得などとして分配される。社会的剰余は、資本の所有者である個人や企業に帰属する。しかし、均等に平等に配分されることは無い。貧富の差を生みだす。これを是正するために財政による「所得の再配分」が必要となる。その為に社会的剰余に課税するのである。課税の対象たる「税源」は社会的剰余に求めるべきである。現代社会では社会的基礎をなす生活費も社会的剰余も「所得」として現象する。社会的剰余たる「所得」への課税こそが現代税法の使命であると考える。「所得」を課税対象とする所得税、法人税こそが「基幹税」にふさわしいと言える。生活費課税たる消費税は「基幹税」などではありえない。消費税は「利益」に税負担をもとめることはない。消費税「基幹税」論は、大企業、大資産家への利益を擁護する理論である。

 社会的基礎部分も社会的剰余部分も、所得として現象する。飲食、住居、服装などの生活費部分は、毎日消費されていく。手元に残ることはない。生活費非課税の考えは、この生活費部分を課税対象から除く考えである。現行の所得税法では、生活費非課税部分を各種所得控除で規定している。 社会的基礎部分も社会的剰余部分も、所得として現象する。飲食、住居、服装などの生活費部分は、毎日消費されていく。手元に残ることはない。生活費非課税の考えは、この生活費部分を課税対象から除く考えである。現行の所得税法では、生活費非課税部分を各種所得控除で規定している。

 社会的に生活費を保障する制度として、最低賃金制度、雇用保険制度、生活保護制度などがある。税法の生活費非課税制度もこれらの諸制度との関連の中で位置付ける必要があると考える。民主党政権は、「所得控除から給付付き税額控除へ」を税制改革の一つの柱としている。その理由を、税負担の有利不利の視点でとらえている。しかし、これは、共通番号制、歳入庁の創設、罰則強化という機構づくりの口実にすぎない。所得控除は、生活号制度」「インボイス制度」「歳入庁の創設」「罰則の強化」などの納税環境整備によって国民の批判をかわし、「基幹税」にふさわしい税目にしようとしている。しかし、生活費に対する課税である消費税が「基幹税」たることを、国民が許すことはない。税収の安定性が「基幹税」の要件ではない。そもそも「租税」の対象となる税源をどこに求めるか、現行消費税の実態、問題点はどこにあるかを検討する中で、「基幹税」とは何かを考える。 社会的に生活費を保障する制度として、最低賃金制度、雇用保険制度、生活保護制度などがある。税法の生活費非課税制度もこれらの諸制度との関連の中で位置付ける必要があると考える。民主党政権は、「所得控除から給付付き税額控除へ」を税制改革の一つの柱としている。その理由を、税負担の有利不利の視点でとらえている。しかし、これは、共通番号制、歳入庁の創設、罰則強化という機構づくりの口実にすぎない。所得控除は、生活号制度」「インボイス制度」「歳入庁の創設」「罰則の強化」などの納税環境整備によって国民の批判をかわし、「基幹税」にふさわしい税目にしようとしている。しかし、生活費に対する課税である消費税が「基幹税」たることを、国民が許すことはない。税収の安定性が「基幹税」の要件ではない。そもそも「租税」の対象となる税源をどこに求めるか、現行消費税の実態、問題点はどこにあるかを検討する中で、「基幹税」とは何かを考える。 |
 |
(1)社会的剰余等が本来の税源

 社会的視点で見た時、税負担は社会的剰余に求められるべきである。資本主義社会では、社会的剰余は個人や企業に帰属する。会計上の「利益」である。社会的剰余は、現象としては、利益だけでなく、利子、配当、地代、家賃、役員給与などの形態をとる。 社会的視点で見た時、税負担は社会的剰余に求められるべきである。資本主義社会では、社会的剰余は個人や企業に帰属する。会計上の「利益」である。社会的剰余は、現象としては、利益だけでなく、利子、配当、地代、家賃、役員給与などの形態をとる。

 社会が継続的に活動していく為には、その成員一人一人の飲食、住居、衣服が満たされている必要がある。いかなる時代であれ生活が充足されなければ社会は成り立たないのである。これが社会の基礎をなす。人間はその社会活動の中でこの社会的基礎を超える剰余を生みだす。自らの再生産(生活)に必要なるもの以上を生みだす。これが社会的剰余である。社会的剰余が誰に帰属するのか、どの様な方法で蓄積、分配されるのかで社会のあり方が異なる。 社会が継続的に活動していく為には、その成員一人一人の飲食、住居、衣服が満たされている必要がある。いかなる時代であれ生活が充足されなければ社会は成り立たないのである。これが社会の基礎をなす。人間はその社会活動の中でこの社会的基礎を超える剰余を生みだす。自らの再生産(生活)に必要なるもの以上を生みだす。これが社会的剰余である。社会的剰余が誰に帰属するのか、どの様な方法で蓄積、分配されるのかで社会のあり方が異なる。

 生活費をまかなう社会的基礎部分は、労働者の賃金、給与として、あるいは零細事業者の事業所得などとして分配される。社会的剰余は、資本の所有者である個人や企業に帰属する。しかし、均等に平等に配分されることは無い。貧富の差を生みだす。これを是正するために財政による「所得の再配分」が必要となる。その為に社会的剰余に課税するのである。課税の対象たる「税源」は社会的剰余に求めるべきである。現代社会では社会的基礎をなす生活費も社会的剰余も「所得」として現象する。社会的剰余たる「所得」への課税こそが現代税法の使命であると考える。「所得」を課税対象とする所得税、法人税こそが「基幹税」にふさわしいと言える。生活費課税たる消費税は「基幹税」などではありえない。消費税は「利益」に税負担をもとめることはない。消費税「基幹税」論は、大企業、大資産家への利益を擁護する理論である。 生活費をまかなう社会的基礎部分は、労働者の賃金、給与として、あるいは零細事業者の事業所得などとして分配される。社会的剰余は、資本の所有者である個人や企業に帰属する。しかし、均等に平等に配分されることは無い。貧富の差を生みだす。これを是正するために財政による「所得の再配分」が必要となる。その為に社会的剰余に課税するのである。課税の対象たる「税源」は社会的剰余に求めるべきである。現代社会では社会的基礎をなす生活費も社会的剰余も「所得」として現象する。社会的剰余たる「所得」への課税こそが現代税法の使命であると考える。「所得」を課税対象とする所得税、法人税こそが「基幹税」にふさわしいと言える。生活費課税たる消費税は「基幹税」などではありえない。消費税は「利益」に税負担をもとめることはない。消費税「基幹税」論は、大企業、大資産家への利益を擁護する理論である。

 社会的基礎部分も社会的剰余部分も、所得として現象する。飲食、住居、服装などの生活費部分は、毎日消費されていく。手元に残ることはない。生活費非課税の考えは、この生活費部分を課税対象から除く考えである。現行の所得税法では、生活費非課税部分を各種所得控除で規定している。 社会的基礎部分も社会的剰余部分も、所得として現象する。飲食、住居、服装などの生活費部分は、毎日消費されていく。手元に残ることはない。生活費非課税の考えは、この生活費部分を課税対象から除く考えである。現行の所得税法では、生活費非課税部分を各種所得控除で規定している。

 社会的に生活費を保障する制度として、最低賃金制度、雇用保険制度、生活保護制度などがある。税法の生活費非課税制度もこれらの諸制度との関連の中で位置付ける必要があると考える。民主党政権は、「所得控除から給付付き税額控除へ」を税制改革の一つの柱としている。その理由を、税負担の有利不利の視点でとらえている。しかし、これは、共通番号制、歳入庁の創設、罰則強化という機構づくりの口実にすぎない。所得控除は、生活費非課税制度を他の社会政策との関連の中で、どの様にとらえるのかという問題であると考える。生活費非課税制度の視点からは、所得控除こそがそのあり方を正しく反映するものと考える。 社会的に生活費を保障する制度として、最低賃金制度、雇用保険制度、生活保護制度などがある。税法の生活費非課税制度もこれらの諸制度との関連の中で位置付ける必要があると考える。民主党政権は、「所得控除から給付付き税額控除へ」を税制改革の一つの柱としている。その理由を、税負担の有利不利の視点でとらえている。しかし、これは、共通番号制、歳入庁の創設、罰則強化という機構づくりの口実にすぎない。所得控除は、生活費非課税制度を他の社会政策との関連の中で、どの様にとらえるのかという問題であると考える。生活費非課税制度の視点からは、所得控除こそがそのあり方を正しく反映するものと考える。 |
 |
(2)消費税の5つの問題点

 庶民にとって消費税は「公平」か? 5つの問題点をみておきたい。消費税のもつ5つの問題点とは、 庶民にとって消費税は「公平」か? 5つの問題点をみておきたい。消費税のもつ5つの問題点とは、 生活、くらし破壊税、 生活、くらし破壊税、 福祉破壊税、 福祉破壊税、 営業破壊税、 営業破壊税、 雇用破壊税、 雇用破壊税、 大企業のもうけ促進税、の5点である。以下、利益に対する課税である所得税、法人税と比較しながら考えてみる。 大企業のもうけ促進税、の5点である。以下、利益に対する課税である所得税、法人税と比較しながら考えてみる。 |
 |
 消費税は生活、くらし破壊税 消費税は生活、くらし破壊税

 消費税は、広く消費に課税する。事業活動での消費は、仕入税額控除により実質負担はない。150円のペットボトルのお茶は、142円の本体価格と8円の消費税である。生活的消費では、150円の支払となる。しかし、事業的消費では、8円分の消費税は仕入の税額控除の対象となり負担から控除される。事業者にとっては、ペットボトルのお茶は142円なのである。一物二価となっている。消費税は、広く消費に対して課税としているが、事業的消費は実質的に課税されない。生活的消費への課税となっている。生活費課税なのである。庶民は消費税があることにより、その分高い買い物をさせられる。消費税分生活費が高くなるのである。収入が同じであれば、消費税分生活費を削らなければならない。消費税は生活、くらしを直撃する税金であり、生活、くらし破壊税と言える。 消費税は、広く消費に課税する。事業活動での消費は、仕入税額控除により実質負担はない。150円のペットボトルのお茶は、142円の本体価格と8円の消費税である。生活的消費では、150円の支払となる。しかし、事業的消費では、8円分の消費税は仕入の税額控除の対象となり負担から控除される。事業者にとっては、ペットボトルのお茶は142円なのである。一物二価となっている。消費税は、広く消費に対して課税としているが、事業的消費は実質的に課税されない。生活的消費への課税となっている。生活費課税なのである。庶民は消費税があることにより、その分高い買い物をさせられる。消費税分生活費が高くなるのである。収入が同じであれば、消費税分生活費を削らなければならない。消費税は生活、くらしを直撃する税金であり、生活、くらし破壊税と言える。

 収入の低い世帯ほど、収入に占める生活費の割合は高くなる。当然、収入に対する消費税の割合も高くなる。消費税の逆進性の問題である。又、消費税は、消費にあてる収入の質を問わない。勤労で得た収入か、そうでないかは問題とならない。 収入の低い世帯ほど、収入に占める生活費の割合は高くなる。当然、収入に対する消費税の割合も高くなる。消費税の逆進性の問題である。又、消費税は、消費にあてる収入の質を問わない。勤労で得た収入か、そうでないかは問題とならない。

 所得税では、原則として生活費非課税である。納税者本人の控除分としての基礎控除額は、38万円である。1995年に35万円から38万円に引き上げられ、以来、同額のまま。38万円は、1日1041円。生活費非課税の額としてはあまりにも少額である。しかし、所得税には生活費に課税しないという考えは存在する。又、給与所得控除にみられる勤労所得軽課税の考えも存在する。 所得税では、原則として生活費非課税である。納税者本人の控除分としての基礎控除額は、38万円である。1995年に35万円から38万円に引き上げられ、以来、同額のまま。38万円は、1日1041円。生活費非課税の額としてはあまりにも少額である。しかし、所得税には生活費に課税しないという考えは存在する。又、給与所得控除にみられる勤労所得軽課税の考えも存在する。 |
 |
 消費税は福祉破壊税 消費税は福祉破壊税

 「消費税は福祉のため!」は創設以来の政府のスローガンである。消費税収が、福祉のためでなく、大企業の減税財源となっていた。これが実態である。使途の不明確さに対し、社会保障目的税化の方向が示されている。この点は別途論ずる。 「消費税は福祉のため!」は創設以来の政府のスローガンである。消費税収が、福祉のためでなく、大企業の減税財源となっていた。これが実態である。使途の不明確さに対し、社会保障目的税化の方向が示されている。この点は別途論ずる。

 消費税は生活費に対して負担を求めている。リストラされて失業し、雇用保険の給付で生活していても消費税の負担はついてくる。病気、事故、高齢化、失職などで収入が途絶え、生活保護費の給付で生活しても消費税の負担はついてくる。生きてゆくことに負担を求めるのが消費税である。福祉の精神に真っ向から反する税と言える。 消費税は生活費に対して負担を求めている。リストラされて失業し、雇用保険の給付で生活していても消費税の負担はついてくる。病気、事故、高齢化、失職などで収入が途絶え、生活保護費の給付で生活しても消費税の負担はついてくる。生きてゆくことに負担を求めるのが消費税である。福祉の精神に真っ向から反する税と言える。

 所得税では、雇用保険給付や生活保護給付は非課税である。収入が無ければ、課税そのものが無い。 所得税では、雇用保険給付や生活保護給付は非課税である。収入が無ければ、課税そのものが無い。 |
 |
 消費税は営業破壊税 消費税は営業破壊税

 事業者は、売上にかかる消費税額から仕入にかかる消費税額を差し引いて申告、納税する。売上代金の集金に際して、消費税分を値引きさせられたらどうなるか。売上にかかる消費税額はゼロとできるか。消費税法は、集金した額を消費税込みの売上金とみる。消費税は「転嫁」を保障していない。事業者にとって、消費税を売上に転嫁できるか否かは、力関係にある。経済力や資本力による。 事業者は、売上にかかる消費税額から仕入にかかる消費税額を差し引いて申告、納税する。売上代金の集金に際して、消費税分を値引きさせられたらどうなるか。売上にかかる消費税額はゼロとできるか。消費税法は、集金した額を消費税込みの売上金とみる。消費税は「転嫁」を保障していない。事業者にとって、消費税を売上に転嫁できるか否かは、力関係にある。経済力や資本力による。

 大企業が中小企業より経済力は強い。親会社が下請会社より経済力は強い。消費税を転嫁できない事業者は、その分売上減少となり、利益の減少となる。利益を削っての消費税の納税となる。中小事業者にとっては、営業破壊税と言える。 大企業が中小企業より経済力は強い。親会社が下請会社より経済力は強い。消費税を転嫁できない事業者は、その分売上減少となり、利益の減少となる。利益を削っての消費税の納税となる。中小事業者にとっては、営業破壊税と言える。

 所得税、法人税は、利益に対する課税である。売上値引きで利益が減少すれば、税負担も減少する。赤字ならば税負担は無い。 所得税、法人税は、利益に対する課税である。売上値引きで利益が減少すれば、税負担も減少する。赤字ならば税負担は無い。 |
 |
 消費税は雇用破壊税 消費税は雇用破壊税

 消費税は、「国内において、事業者が、対価を得て、事業として行う、資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供」に対して課される。労働者の給与はどうなるか。労働者は事業者ではないので、対価を得て役務の提供をしていても課税取引ではない。しかし、同じ仕事でも、外注となると意味合いは異なってくる。事業者による役務の提供となり、課税取引となる。月額40万円の給与の支払いも、外注であれば38万円余の外注費とそれにかかる消費税2万円となる。損益計算では、給与40万円から外注費38万円と、経費の減少、利益の増加である。消費税の申告では、仕入にかかる消費税が2万円増となり、差引消費税の納税は2万円の減となる。企業にとっては、直接雇用から派遣労働者に切り換えることは、利益をもたらし、消費税の納税を減らすことになる。消費税はリストラ促進税であり、雇用破壊税である。 消費税は、「国内において、事業者が、対価を得て、事業として行う、資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供」に対して課される。労働者の給与はどうなるか。労働者は事業者ではないので、対価を得て役務の提供をしていても課税取引ではない。しかし、同じ仕事でも、外注となると意味合いは異なってくる。事業者による役務の提供となり、課税取引となる。月額40万円の給与の支払いも、外注であれば38万円余の外注費とそれにかかる消費税2万円となる。損益計算では、給与40万円から外注費38万円と、経費の減少、利益の増加である。消費税の申告では、仕入にかかる消費税が2万円増となり、差引消費税の納税は2万円の減となる。企業にとっては、直接雇用から派遣労働者に切り換えることは、利益をもたらし、消費税の納税を減らすことになる。消費税はリストラ促進税であり、雇用破壊税である。 |
 |
 消費税は、大企業のもうけ促進税 消費税は、大企業のもうけ促進税

 消費税は、広く消費に対して負担を求める税である。しかし、事業的消費については、売上に消費税を転嫁できれば、実質上、負担は無い。大企業ほど売上への転嫁は可能である。大企業は、1円も消費税を負担していない。むしろ、下請けからの消費税転嫁を許さない、あるいはリストラにより正社員を外注に転換すれば、大きな利益がもたらされる。これが、日本経団連が、法人税率の引き下げと消費税率の引き上げを要求する理由である。 消費税は、広く消費に対して負担を求める税である。しかし、事業的消費については、売上に消費税を転嫁できれば、実質上、負担は無い。大企業ほど売上への転嫁は可能である。大企業は、1円も消費税を負担していない。むしろ、下請けからの消費税転嫁を許さない、あるいはリストラにより正社員を外注に転換すれば、大きな利益がもたらされる。これが、日本経団連が、法人税率の引き下げと消費税率の引き上げを要求する理由である。

 消費税は、株や土地取引は非課税である。配当や利子取引も非課税である。大資産家の投資活動には負担を求めないのである。大企業、大資産家には、圧倒的に有利な税制と言える。大企業は利益から消費税を負担することは無い。消費税「基幹税」論は、大企業、大資産家擁護論でもある。 消費税は、株や土地取引は非課税である。配当や利子取引も非課税である。大資産家の投資活動には負担を求めないのである。大企業、大資産家には、圧倒的に有利な税制と言える。大企業は利益から消費税を負担することは無い。消費税「基幹税」論は、大企業、大資産家擁護論でもある。

 以上みてきた様に、消費税は、その税源をどこに求めるかという「税源論」の視点からも、現行消費税のもつ5つの問題点の視点からも、「基幹税」たる資格は無い。(表2参照) 以上みてきた様に、消費税は、その税源をどこに求めるかという「税源論」の視点からも、現行消費税のもつ5つの問題点の視点からも、「基幹税」たる資格は無い。(表2参照) |
 |