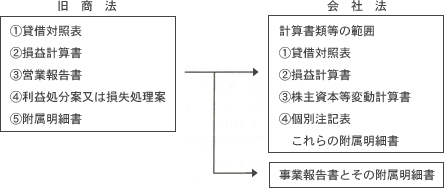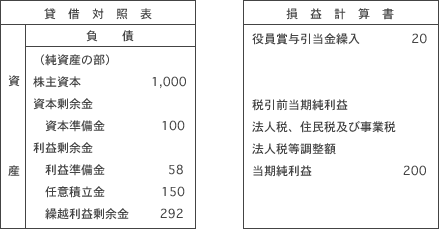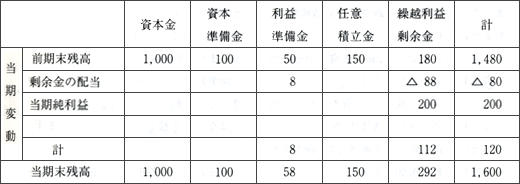| (1) |
 株式会社(特例有限会社を含む)は、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の4つをいう)を作成しなければなりません(435条 株式会社(特例有限会社を含む)は、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の4つをいう)を作成しなければなりません(435条 、計算規則91条 、計算規則91条 〜 〜 )。なお、この4つの計算書類は省略できませんが、それぞれを構成するものごとに一つの独立した書面資料として作成しなくとも良いことになっており(計算規則89条 )。なお、この4つの計算書類は省略できませんが、それぞれを構成するものごとに一つの独立した書面資料として作成しなくとも良いことになっており(計算規則89条 )、貸借対照表あるいは損益計算書等と一体表示しても構わないことになっています。 )、貸借対照表あるいは損益計算書等と一体表示しても構わないことになっています。 |
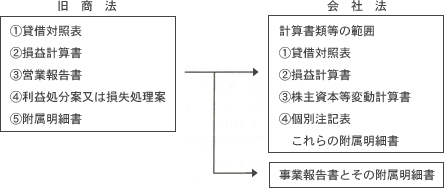 |
 |
| (2) |
 年中いつでも株主総会の決議により剰余金の配当ができることと役員賞与も役員の職務執行の対価と位置づけられ、会計上、発生した事業年度の費用処理することになりました(役員賞与に関する会計基準第1項)。したがって、従来のように利益処分としての配当や役員賞与の支出を決算承認時に株主総会で決める必要がなくなったことから、5月決算期から計算書類が新しく変わる時期に合わせ、利益処分案(又は損失処理案)の作成が廃止されました(改正財務諸表等規則でも削除されました)。 年中いつでも株主総会の決議により剰余金の配当ができることと役員賞与も役員の職務執行の対価と位置づけられ、会計上、発生した事業年度の費用処理することになりました(役員賞与に関する会計基準第1項)。したがって、従来のように利益処分としての配当や役員賞与の支出を決算承認時に株主総会で決める必要がなくなったことから、5月決算期から計算書類が新しく変わる時期に合わせ、利益処分案(又は損失処理案)の作成が廃止されました(改正財務諸表等規則でも削除されました)。 |
 |
| (3) |
貸借対照表の変化する点は、次のとおりです。 |
| |

 |
資産の部の繰延資産の表示が厳密になります。税務上の繰延資産は、投資その他の資産の部の中の長期前払費用勘定で会計処理するとともに、会社法上の繰延資産は5項目に限定されます(近く公表される企業会計基準委員会による繰延資産に係る実務対応報告では創立費、開業費、開発費、社債発行費等、株式交付費の5項目)。しかも資産計上された月から月割計算による相当の償却をしなければなりません。
 |
| |

 |
旧資本の部が純資産の部という表示に変わります。純資産の部は正味財産を表すものではなく、資産から負債を差し引いた差額としての性格で、その中は3つに分かれています。1つが剰余金の配当原資となる株主資本です。2つが有価証券や土地などの評価・換算差額です。3つが新株予約権です(計算規則108 )。 )。
 |
| |

 |
従来、会社が取得した自己株式を資産科目で計上していましたが、計算書類の変化に合わせ、株主資本の中の項目としてマイナス表示することになりました。今までに取得し、帳簿残高がある自己株式は、この際合計額を株主資本に振替えてマイナス表示をしなければなりません(同規則108 )。 )。
 |
| |

 |
その他として、営業権が「のれん」勘定に、子会社株式が「関係会社株式」勘定に変わります。当期利益は、「その他利益剰余金の内訳科目である繰越利益剰余金」として記載されます。 |
 |
| (4) |
損益計算書の変化する主な点は、次のとおりです。 |
| |

 |
経常損益の部や特別損益の部という区分がなくなります(計算規則119条)。売上高から売上原価を差し引いて売上総利益を表示し、売上総利益から販売費及び一般管理費を差し引いて営業利益を表示するように、従来どおりの縦流しの項目表示で末尾は当期純利益で止めることになります(同規則120〜125)。その結果、従前の前期繰越損益以下が削除されることになります(改正財務諸表等規則では既に削除されました)。 |
| |

 |
役員賞与も「職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益」と会社法で位置づけられました(会361 )ので、税務上も役員給与として一本化されました(改正法人税法34)。 )ので、税務上も役員給与として一本化されました(改正法人税法34)。 |
| |

 |
従来の決算役員賞与を計上するのであれば、事業年度末において、会計上、役員賞与引当金繰入額/役員賞与引当金を計上して当該事業年度の決算に組み込んだうえ、税務上、別表加算することになります。 |
 |
| (5) |
株主資本等変動計算書ですが、全く新し い形式表示です。 |
| |

 |
貸借対照表の純資産の部の各項目を前期末残高、当期変動額、当期末残高に区分して表示します。この計算書は、剰余金の配当が年中いつでもできることから、前期末残高が必ずしも同額で当期末まで残っていないので、純資産の部の項目ごとに移動を表すものとして作成されることになりました。株主資本項目の当期変動額は変動事由ごとに区分表示して、変動経緯を示すことになります(計算規則127 )。評価・換算差額欄、新株予約権欄は変動額の純額表示でよいことになります(同規則127 )。評価・換算差額欄、新株予約権欄は変動額の純額表示でよいことになります(同規則127 )。 )。 |
| |

 |
損益計算書との関係も明らかにするために、当期純利益を利益剰余金の変動事由として必ず記載し(仮に当期純利益がゼロであっても)、その他利益剰余金の内訳としての繰越利益剰余金欄で表示することになります。計算書の全体表示形式は、横長式が原則とされていますが、改正財務諸表等規則では横長様式のみになりました。 |
 |
| (6) |
 12項目の注記項目があります(計算規則129条 12項目の注記項目があります(計算規則129条 )が、会計監査人設置会社以外の公開会社でない株式譲渡制限会社の注記表は9項目が省略でき、多くの中小会社は3項目だけの記載でよいことになります。3項目の注記とは、 )が、会計監査人設置会社以外の公開会社でない株式譲渡制限会社の注記表は9項目が省略でき、多くの中小会社は3項目だけの記載でよいことになります。3項目の注記とは、 重要な会計方針に係る事項に関する注記、 重要な会計方針に係る事項に関する注記、 株主資本等変動計算書に関する注記、 株主資本等変動計算書に関する注記、 その他の注記(いわゆる追記情報他)です。 その他の注記(いわゆる追記情報他)です。
 しかし、会計監査人設置会社以外の公開会社である中小会社は、10項目の注記が必要です。 しかし、会計監査人設置会社以外の公開会社である中小会社は、10項目の注記が必要です。 |
 |
| (7) |
 計算書類の附属明細書の記載内容は、3項目です(計算規則145条)。 計算書類の附属明細書の記載内容は、3項目です(計算規則145条)。 有形・無形固定資産の明細、 有形・無形固定資産の明細、 引当金の明細、 引当金の明細、 販売費及び一般管理費の明細(現行の損益計算書の内訳書)の3つです。 販売費及び一般管理費の明細(現行の損益計算書の内訳書)の3つです。
 以上の計算書類の表示形式は、昨年末からの新報528・530号に掲載されていますので参考にしてください。 以上の計算書類の表示形式は、昨年末からの新報528・530号に掲載されていますので参考にしてください。 |
| (1) |
 利益処分案が廃止されたことに伴い、処分案での配当金支出を決めることができません。その結果、従前のように事業年度と対応させる必要がなくなり、配当の期間対応措置も廃止されることになりました。つまり、剰余金の配当は基準日で処理するのではなく、効力発生時に処理することになりました。剰余金の配当の事実については、株主資本等変動計算書の注記で表すこと(計算規則136条)になりました。 利益処分案が廃止されたことに伴い、処分案での配当金支出を決めることができません。その結果、従前のように事業年度と対応させる必要がなくなり、配当の期間対応措置も廃止されることになりました。つまり、剰余金の配当は基準日で処理するのではなく、効力発生時に処理することになりました。剰余金の配当の事実については、株主資本等変動計算書の注記で表すこと(計算規則136条)になりました。 |
 |
| (2) |
 株主資本等変動計算書に付する注記では、次の 株主資本等変動計算書に付する注記では、次の および および に分けた注記が必要です。この記載がなければ、税務申告の別表による調整は行われませんので記載もれに注意です。 に分けた注記が必要です。この記載がなければ、税務申告の別表による調整は行われませんので記載もれに注意です。 |
| |

 |
当期中に行った配当(前期定時総会で決めた配当)について、株式の種類ごとの配当金総額、1株当たりの配当額、基準日および効力発生日(金銭配当の場合は金銭の総額、現物配当の場合は、配当金総額に代えて配当財産の種類およびその帳簿価額)を記載します。 |
| |

 |
決算日後に行う配当(今期定時総会終了後に支払う予定の配当)の内、基準日が当該事業年度中のものについては、上記 の事項に加え、配当の原資(利益剰余金あるいは資本剰余金のいずれから支出するのか)を記載します。 の事項に加え、配当の原資(利益剰余金あるいは資本剰余金のいずれから支出するのか)を記載します。 |
 |
| (3) |
 会社法適用初年度については、別表関連図を参照してください。別表4では、配当を効力発生日に変更した結果、当期利益は全額社内留保になり、社外流出欄は記入額がありません。当期中の配当金支払額は既に前期の別表4の社外流出欄で処理ずみだからです。また、今期事業年度末までを基準日として、配当の効力発生日が株主総会以後の次年度中に支払う配当は、来期の別表4の社外流出欄で処理されることになります。 会社法適用初年度については、別表関連図を参照してください。別表4では、配当を効力発生日に変更した結果、当期利益は全額社内留保になり、社外流出欄は記入額がありません。当期中の配当金支払額は既に前期の別表4の社外流出欄で処理ずみだからです。また、今期事業年度末までを基準日として、配当の効力発生日が株主総会以後の次年度中に支払う配当は、来期の別表4の社外流出欄で処理されることになります。 |
 |
| (4) |
 さらに、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金や利益準備金の前期末残高と別表5(1)の期首残高とは、会社法適用初年度のみ一致しません(繰越利益剰余金から前期定時総会時の配当・利益準備金額の差し引き後は一致します)。 さらに、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金や利益準備金の前期末残高と別表5(1)の期首残高とは、会社法適用初年度のみ一致しません(繰越利益剰余金から前期定時総会時の配当・利益準備金額の差し引き後は一致します)。
 なお、同族会社の留保金課税の留保所得金額の計算では、決算確定日までに決議される配当額は、基準日控除による減額ができます(法人税法附則43 なお、同族会社の留保金課税の留保所得金額の計算では、決算確定日までに決議される配当額は、基準日控除による減額ができます(法人税法附則43 )。 )。 |