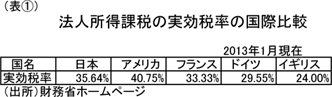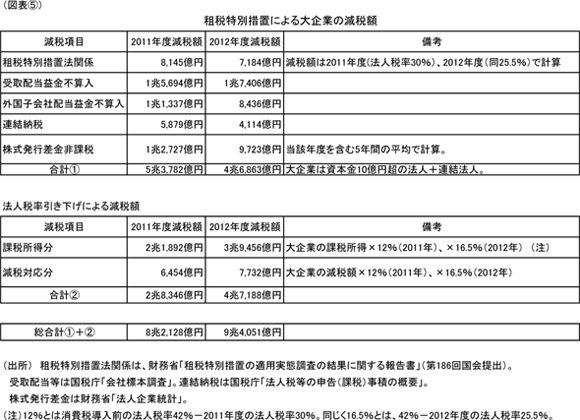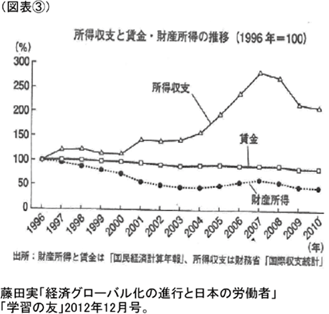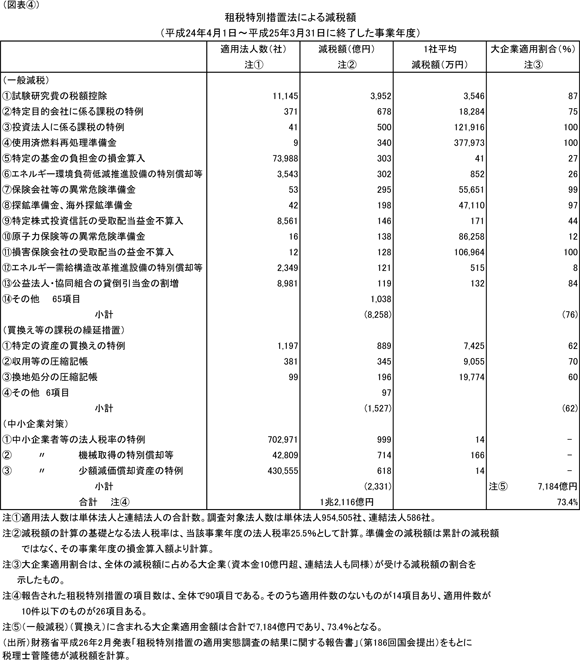法人実効税率と大企業優遇税制 |
| 埼玉会 菅 隆徳 |
| はじめに そこで再び「法人実効税率を引下げの議論を早期に開始すべき」と要請している。2013年9月11日、安倍首相は麻生財務相と甘利経済再生担当相を官邸に呼び、法人実効税率の引き下げを要請した。麻生財務相は、財務省内で協議の後、翌12日に「税率引き下げは無理だが、復興特別法人税の1年前倒し廃止なら可能」と応じた。 2013年12月12日に発表された「平成26年度税制改正大綱」では、法人実効税率について「我が国経済の競争力向上のため法人実効税率を引き下げる環境を作り上げることも重要」とした上で、「課税ベースの拡大や他税目での増収策による財源確保を図る必要がある」と、法人税引き下げの財源のために、さらなる消費税増税を行うことを示唆している。2014年1月、経済財政諮問会議の民間議員が、法人実効税率を現行より10%低い25%程度にすべきと提言。 麻生財務相はこれを受けて、そのための財源は5兆円必要と発言した。安倍首相はスイスのダボス会議で、本年さらなる法人税改革に着手と発言、異次元の税制措置を断行すると述べた。甘利経済再生担当相は、実効税率の引下げは、6月の「骨太方針」にスケジュールを盛り込みたいと述べた。2月13日、政府税制調査会は法人実効税率引き下げについて討議を開始した。太田弘子政府税調法人課税グループ座長は「日本の法人税率が高いのは事実。今度こそ正面から議論しなければ」と述べた。 本稿では、「日本の法人税は高すぎる」という、政府や財界の主張を具体的に検証する。同時に租税特別措置などの大企業優遇税制の実態を分析し、税の公平原則(応能負担原則)に反する、税の不公平がどこにあるかを解明する。あわせて大企業優遇税制の不公平をただせば、8兆円を超える財源が生まれ、消費税増税は必要ないことを、財源面から明らかにする。 |
| 1.日本の法人税は高いのか (1)大企業の税負担の実際 ところが中小企業は市場の競争や下請け関係などから、消費税分を売値に100%上乗せすることが難しい。税務署は「上乗せできなくても、実際の売値が100%上乗せしてあるものとみなして」課税する。だから、上乗せできない分は、結局中小企業が自腹を切って税務署に納付する。市場の力関係によって、弱いものが負担をさせられる、不公平な弱肉強食の税金である。さらに消費者は買い物をするたびに消費税を必ず買値の一部として支払っている。だから、消費税を実質負担しているのは、中小企業と庶民なのである。大企業は1円も負担していない。しかも輸出大企業は輸出戻し税(実質輸出補助金)の還付も受けている。
課税所得×税率ー税額控除=法人税額(納付税額) (100ー30)× 30% ー10 = 11億円となる。 このように税率とは直接関係のない、課税ベースの縮小、税額控除の発生で莫大な大企業減税が発生し、実質税負担率を引き下げているのである。表面税率の比較ではわからない、すさまじい大企業減税が行われている。課税ベースの広さや税額控除の大小は、各国の税制によっても違っている。だから単純な表面税率の比較だけでは、各国の法人税負担の比較はできないのだ。(4) 表面税率だけを取り上げて、日本は法人税が高い、だから大企業の負担も重いという宣伝は、このような大企業減税の実態を隠している。また一方で、実態を隠しながら、優遇されている大企業にさらに税率を引き下げる口実となっている。
「実は日本で本当に国際的に活躍している大企業の実際の税負担率は、実効税率=表面税率ほど高くはありません。それには2つの要因があって、一つ目は政策減税の効果がかなり効いており、研究開発減税だけでも相当な影響があります。その他もろもろの租税特別措置を合わせると、例えば製造業の場合、実際の税負担率は、おそらく30%台前半になります。もう一つは、国際展開している企業は、税金の低い国でかなり事業活動を行っていますから、全世界所得に対する実効税率はそれほど高くない。今ただちに法人実効税率を下げなければならないという理屈はあまりないわけです。」(「国際税制研究」NO.18 2007年 清文社 座談会「抜本的税制改革の諸課題」) この発言は、多国籍化した大企業の税負担の実情を正確に伝えている。尚、ここで言っている「税金の低い国で事業活動」というのは、すでに多国籍化している日本の大企業の海外子会社による海外生産のことである。海外子会社は、アジアなどの低税率国で生産、販売、納税し、それで蓄積した利益を親会社(日本の大企業)へ配当している。後述するように自動車産業では生産の60%以上が海外生産である。その受取配当については、95%非課税として、大企業に莫大な減税をもたらしている。(2011年度の外国子会社配当益金不算入の減税額は、1兆1,337億円に達している。図表 すでに多国籍化している日本の大企業は、海外ではアジアなどの低税率を享受して利益を上げ、国内ではアジア並みへの法人実効税率引き下げで、莫大な利益を上げようとしているのである。(5) 大企業はすでに多国籍化して、それによって充分な国際競争力をもって利益を上げている。一方で、「日本は法人税が高いから大企業が海外へ逃げていく」と国民に脅しをかけ、法人税減税の財源を消費税増税でまかない、中小企業と庶民に負担を押し付けようとしている。
|
この間、日本のGDP(国内総生産)は、名目でも、実質でも2007年をピークにマイナスを記録している。製造業の国内雇用者数は、ピーク時の1992年から500万人減少している。生産面でも、雇用面でも、日本のグローバル企業の成長は、国民経済の発展につながっていない。 |
 |
安倍政権が目指す21世紀の経済構造とは、国内生産基盤の拡充による内需・輸出拡大を可能にするナショナル循環(国民経済内での生産・流通関連の質的高度化)の強化ではなく、グローバル戦略下でのアジア地域に重点を置いた企業内国際分業構造(グローバル循環)の構築である。例えばトヨタ自動車の場合、ピックアップトラックの生産拠点はエンジンがインドネシア、トランスミッションがフィリピン、電子部品がマレーシアにあり、最終組み立てはタイとインドネシアで行われている。日本の大企業は21世紀に入ってからFTA(8) を活用して、輸出拠点を日本から海外に展開してきた。 例えばトヨタは米韓FTAの締結を契機に、アメリカ工場から韓国への輸出に踏み切り、東芝はインドの火力発電用タービン工場の生産能力を2015年度までに倍増し、東南アジアや中近東へ輸出する。こうした海外工場の第三国向け輸出は、2010年度で約15兆8,000億円と10年間で3倍強に拡大した。すなわち大企業はFTAの拡大に対応し、輸出拠点の比重を国内から海外に移し、最適生産地からの輸出に切り替えて国際競争力を強めつつある。(9) 現在では非正規労働者は雇用者全体の3分の1を大きく超え、19から24歳の若年労働者の場合ほぼ2名に1名が非正規を強制されている。そして、非正規の若年労働者の9割は、たとえ正規労働者と同じように週40時間働いたとしても、月収で最大10数万円、年収で200万円未満という非人間的な生活を余儀なくされている。
|
| 2.グローバル企業はきちんと税金を払うべきだ (1)明らかになった大企業優遇税制の実態 適用額明細書の集計結果
2)(一般減税)では大企業利用割合が85%以上となっている項目が、上位10項目中5項目ある。一般減税全体の76%が大企業減税である。大企業は「新幹線鉄道大規模改修準備金」の1社で85億円、「使用済燃料再処理準備金」の1社平均37億円をはじめ、少ない適用件数で、1社当たりの減税額は億単位の多額な減税を受けている。 3)原子力発電関係にも、使用済燃料再処理準備金、9社で340億円、原子力発電施設解体準備金、9社で45億円と多額な減税が行われている。東京電力の有価証券報告書によれば、使用済燃料再処理引当金の残高は、1兆1,627億円(平成24年3月期)となっており、約3,500億円の累計減税額が推定される。 4)投資法人に係る課税の特例(41社で500億円)、特定目的会社に係る課税の特例(371社で678億円)、保険会社等の異常危険準備金(53社で295億円)など、一般になじみの薄い知られていない特例がある。この機会にその特例の根拠を広く明らかにさせ、適正な見直しをさせることが必要ではないか。「補助金であれば常にチェックされる」事項が、「隠れた補助金」であるがゆえに、租税特別措置が一度税制改正で入ると、議会の統制を受けず既得権化して、税制改正によって廃止されるまでは見直しがされづらいのである。 5)買換え等の課税の繰延べ措置においても、大企業利用割合は全体で62%になっており、大半は大企業減税に使われている。以上の1)から5)までの大企業減税額を合計すると、平成24年度分は、7,184億円になる。(法人税率25.5%で計算) (2)租税特別措置法以外の租税特別措置 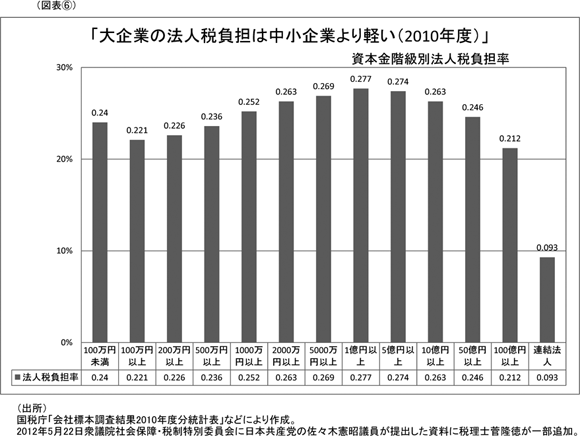 |
| 3.応能負担原則を貫けば、10兆円の財源 (1)消費税導入で法人税収激減 1989年に消費税が導入されるのと同時に法人税率の引下げが始まった。消費税導入前は42%だった法人税率は、40%(89年)→ 37.5%(90年)→ 34.5%(98年)→ 30%(99年)→ 25.5%(2012年)となり、89年に19兆円あった法人税収は11年には8.8兆円にまで落ち込んだ。この間の経済の低迷と、「租税特別措置」・法人税率の引下げが、法人税収の激減を招き、財政危機の大きな原因となっているのだ。従業員1人当たりの賃金がピークだった1997年と2012年を比べると、賃金は604万円から556万円(48万円減少)。大企業の内部留保は142兆円から272兆円へ130兆円も増えている。大企業は賃金を抑え、本来、税金として支払うべき資金を、減税で社外流失を逃れ、内部留保を272兆円にも増やしているのである。法人実効税率の引下げ論議に当たり、安倍首相のいう「大企業がもうかれば、それが中小企業や庶民にも及ぶ」というのは、これらの事実を見るときに、歴史的事実に反するのではないかと思われる。 (2)大資産家にも適正な課税を |
| 注 (1)法人税の実効税率というのは、地方税分も含めた法人所得課税の税率を計算したもの。法人所得課税には国税である「法人税」と、地方税である「法人住民税」「法人事業税と地方法人特別税」がある。このうち、法人事業税と地方法人特別税は、法人の所得を計算するときに「費用」として損金に算入できるが、法人税と法人住民税はできない。この損金算入の影響を調整して計算したのが「実効税率」だ。従来は39.54%(約40%)、2012年4月以降は35.64%となっている。各種の租税特別措置を反映した「実質負担率」は、これよりさらに低くなる場合がある。「実質負担率」は決算書から、法人税等(実際の納税額)÷ 税引前当期利益で計算する。 (2)日本経済新聞2013年8月13日 (3)実際の大企業の税負担率が、表面税率よりもずっと低い点について、垣内亮氏が計算し発表している。垣内氏の計算によれば、実際の税負担率は、大企業上位50社で33.0%、上位100社で33.4%、上位200社で33.6%、上位300社で33.8%となっている。(法人実効税率が40%だった、2003から2010年度の8年間の実績の平均)(垣内亮「消費税が日本をダメにする」2012年、新日本出版社) (4)単純な表面税率の比較だけで国際比較はできないという点について、「税研」172号(2013年11月)では、次のようなレポートがある。アメリカの法人実効税率は40%前後であるものの、様々な優遇税制の活用により、多くのアメリカ多国籍企業の実効税率は、20%台に留まっている。ドイツでは、2008年法人税率、営業税の基本税率の大幅引き下げ(引き下げ後の実効税率は約30%)があったが、それに伴って課税ベースの拡大も行われている。営業税の損金算入が認められなくなった。支払利息の損金算入制限が設けられた。また、イギリスやドイツは実効税率の引下げに合わせて、減価償却制度を縮小した。ドイツは2008年に定率法を廃止した。実効税率を30%へ9%引下げて316億ユーロ(4兆4000億円)減税する一方、定率法廃止などで266億ユーロ(3兆7000億円)の増収とした。(日本経済新聞2014年4月8日付) (5)日産自動車の志賀俊之COO は、朝日新聞(2013年7月1日付)のインタビューで次のように述べている。「日産も売上の半分、営業利益も6割を海外で稼いでいるが、海外子会社からの配当などの形で国内に利益を戻し、納税もしている」外国子会社からの配当が95%非課税で、大減税になっていることには何も触れていない。 (6)米田貢「日本経済の現局面と国民生活向上のための基本戦略政治」「学習の友」2013春闘別冊号。2013年1月。学習の友社。 (7)米田貢 前掲書 (8)FTAは自由貿易協定のこと。物品の関税、その他の制限的な通商規則、サービス貿易等の障壁など、通商上の障壁を取り除く自由貿易地域の結成を目的とした、2国間以上の国際協定。 (9)吉田敬一「持続可能な経済構造と中小企業」「中小企業問題」2014年1月発行、NO.141.公益財団法人政治経済研究所。 (10)藤田実「経済グローバル化の進行と日本の労働者」「学習の友」2012年12月号。学習の友社。 (11)藤田実 前掲書 (12)垣内亮「消費税によらなくても社会保障の財源はある」「学習の友」2014年3月号。学習の友社。 (13)北野弘久「税法学原論」(第6版)2007年。青林書院。 |
(すが・たかのり) |
| ▲上に戻る |