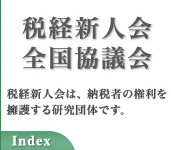
| 第42回 |
>>第42回 |
| 経営指針作り | |
| 埼玉会 |
|
埼玉中小企業家同友会の「経営指針作り」セミナーを主催したり、各地区会へ指針作りの援助に入ったりしている経営委員会の社長たちが参加するのでできれば25名以上はと思っていましたのでほっとしましたし、想像以上に関心があるのだという気がします。 また、何人かお世話になった古い会員の方もいて、いつもの取り組みを紹介するということを中心にどのようなレベルの報告にしたらいいのかも十分に揉まないうちの発表でしたから何とか無事に終わったかなと言うのが本当のところでしょうか。 |
さらに、雑誌シリエズの最近の特集を出しながら、記帳代行会社の増加、記帳代行会社の記帳料が安いのは仕訳数量に応じて設定していることと、申告については重きを置かない関わりによると報告をしました。おのずと会計事務所と目的が違うが、記帳代行会社が増えている事実は指摘をしました。 また、顧問料の水準、顧客数の増減を示してシリエズの調査では顧客の増加傾向、顧問料の増加傾向があると報告をしました。その中に経営関与は含まれていない。つまり、経営関与はシリエズの調査をしても新しい顧問関与の要素として顧問料を引き上げる可能性を持っていることを示していることを報告しました。 |
土木設計は公共工事がほとんどでサブゼネコンの下請けのような仕事がほとんどです。公共工事が減っていく厳しい経営環境の中でご多分に漏れず売上が下がり、社員のモチベーションも上がらない状況の中で指針作りに挑戦をして経営理念や方針・計画を社員と共有化することに力を尽くし会社を変えてきました。売上を伸ばし利益が出せる会社になりつつあります。 その勢いのある報告は、私が経営指針作りセミナーの責任者として7年も関わってきた喜びを表すものです。顧問先の関与の中で会社が眼に見えて変わることというのはなかなか難しいものですが、数年の間で大きく成長していく社長を見るのは本当に楽しいものです。 私は、辛口コメントで埼玉のセミナーでは有名で歯に絹を着せぬ批評で鳴らしています。税理士が、関与の中でお客様の経営の変化を作り出すことができて、お客様を元気にできる、このような関与ができればというのは誰もが思うのではないでしょうか。この会社の関与税理士は私の知っている同友会の会員の税理士で指針作りにも参加をしていましたが、まったく作る経過では声も聞いていないといっていました。税理士と経営関与古くて新しいテーマではないでしょうか。 |
というのも、社長自身が自身の存在価値や自社の魅力、社会的な貢献についての問いかけを行い、掴み取ることを目指すからです。社長が変わらなければ会社は変わらない。自分は何のために経営しているのかを掴むためです。まさに、社長自身の自己発見の旅と言っても過言ではありません。そこでは「科学性・社会性・人間性」の視点で自社のあり方を追求し社会に対する貢献、自社の存在価値を掴み確信にすることが求められます。 このような取り組みの中で、厳しい経営環境をしのいで経営に確信を持ったり社長が大きく変わる姿を幾つか見ています。社長と言うのは会社ではある意味自分の思うようにやっています。そのような社長が各種シートに悪戦苦闘しながら記入して自分の思いを描きそこから自社の姿をつかんで行きます。シートを見ながら様々なアドバイスをして、小さなヒントから確信を持ってもらうことができ、社長の納得する理念や計画が作り出されたときにはいろいろな意味で社長とも心が通い合うような思いを持ちます。まったくお金にはなりませんが指針作りの運動にのめり込んでいる理由がそこにあります。 |
| ・「埼玉中小企業家同友会」とはどのような組織ですか |
| ・「ISO」とは何ですか |
そのために能力開発をどのように進めるか頭を痛めているのが実情です。そこまでを基本サービスとしても、指針作りはまったくできません。その程度では作れないのです。やはり、これも税務会計から離れて、経営に対する一定の基礎知識とお客様をつかみ力を引き出し、纏め上げて作り上げる力が必要です。税務会計のAの力量が経験ある税理士であるならば経営関与のAの力量も、お客様に実際に理論ではなく、ISOの取得支援ができる、経営指針作りができる力量が必要とされるのです。 たまたま私は、現在の第一経営が5つの事務所を持ち100人からの企業になっていますので、経営指針を作り、ISOの取得にも一貫して加わって取得に参加をしました。税理士と言う仕事は多くの所員に任せて経営関与の知識とスキルを磨いてきたと言えます。経営者であったためにできたといっても良いのではないでしょうか。それが前述の「封印」という表現になっています。つまり「専門家」レベルをどのように作り上げるかレベルをどのように捉えるかではないでしょうか。 |
| ・「ISOは、コストが高く、資料作りに時間がとられ、本質的なものを見失うデメリットがあるのではないか」 |
(ぬまた・みちたか) |
| ▲上に戻る |